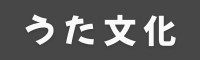国際ニュースやスポーツ大会で耳にする機会がありながら、その独特の短調の響きにどこか心がざわつく感覚を覚えたことはないでしょうか。
イスラエル国歌「ハティクヴァ」の歌詞や意味を知ろうとすると、そこには単なる愛国心を超えた複雑な歴史や感情が見え隠れします。
また、音楽の授業で習ったスメタナのモルダウに似ていると感じて、その理由やハティクヴァの歴史について詳しく調べたくなった方も多いはずです。
物悲しくも美しい旋律がなぜ「怖い」と表現されることがあるのか、その背景にある物語を紐解いていきましょう。
- ハティクヴァが国歌として成立するまでの複雑な歴史的経緯
- 歌詞に込められた2000年の希望とユダヤ人の魂の意味
- スメタナの「モルダウ」とメロディが似ている音楽学的な理由
- 現代社会における国歌を巡る政治的な論争や課題
イスラエル国歌の歌詞の意味と歴史

イスラエル国歌「ハティクヴァ」は、世界中の国歌の中でも特に数奇な運命をたどってきた楽曲の一つと言えます。
ここでは、この曲がどのようにして生まれ、どのような言葉で紡がれ、そしてなぜこれほどまでに人々の心を揺さぶるのか、その歴史的背景と歌詞の深層について掘り下げていきます。
ハティクヴァの歴史と成立過程
「ハティクヴァ」が現在の地位を確立するまでの道のりは、決して平坦なものではありませんでした。
19世紀後半、まだイスラエルという国家が存在しなかった時代に、詩人ナフタリ・ヘルツ・インベルによって書かれた詩「Tikvatenu(我々の希望)」がすべての始まりです。
インベルは放浪の詩人であり、今日、私たちがイメージするような厳格な宗教家ではありませんでしたが、彼の言葉は離散していたユダヤ人たちの心に深く刺さりました。
その後、サミュエル・コーエンという人物が民謡のメロディをこの詩にのせたことで、歌としての「ハティクヴァ」が誕生します。
特筆すべきは、この曲が当初から「国歌」として作られたわけではないという点です。
長らくシオニズム運動の愛唱歌として親しまれ、1948年の建国時にも事実上の国歌として歌われましたが、法的に正式な国歌として定められたのは、驚くべきことに2004年になってからのことでした。
さらに2018年の基本法制定によってその地位は盤石なものとなりましたが、この長い空白期間こそが、イスラエルという国家の成り立ちの複雑さを物語っていると言えるでしょう。
歌詞の和訳とカタカナでの読み方
ヘブライ語で歌われるこの国歌は、日本人にとってはなじみのない響きかもしれませんが、その内容は非常に情緒的です。
まずは、現在歌われている1番とリフレイン(繰り返し部分)の読み方と、その大まかな意味を確認してみましょう。
1番
コル・オド・バッレヴァヴ・ペニマ(心の奥底にある限り)
ネフェシュ・イェフディ・ホミヤー(ユダヤ人の魂が切望し)
ウルファアテイ・ミズラッハ・カディマ(そして東の果てへ、前方へ)
アイン・ルツィヨン・ツォフィヤー(目がシオンを見つめる)
リフレイン
オド・ロ・アヴダ・ティクヴァテヌ(我々の希望はまだ失われていない)
ハティクヴァ・バット・シュノット・アルパイム(2000年の希望)
リヒヨタ・アム・ホフシ・バルツェヌ(我々の土地で自由な民となること)
エレツ・ツィヨン・ヴィルシャライム(シオンとエルサレムの地において)
このように、歌詞には具体的な地名や「2000年」という時間の長さが刻まれています。
ヘブライ語という言語自体が持つ響きの不思議さや、古代から続く言葉の重みに興味を持たれた方は、日本の国歌との意外な関連説についても調べてみると面白い発見があるかもしれません。
ハティクヴァの意味と希望の象徴
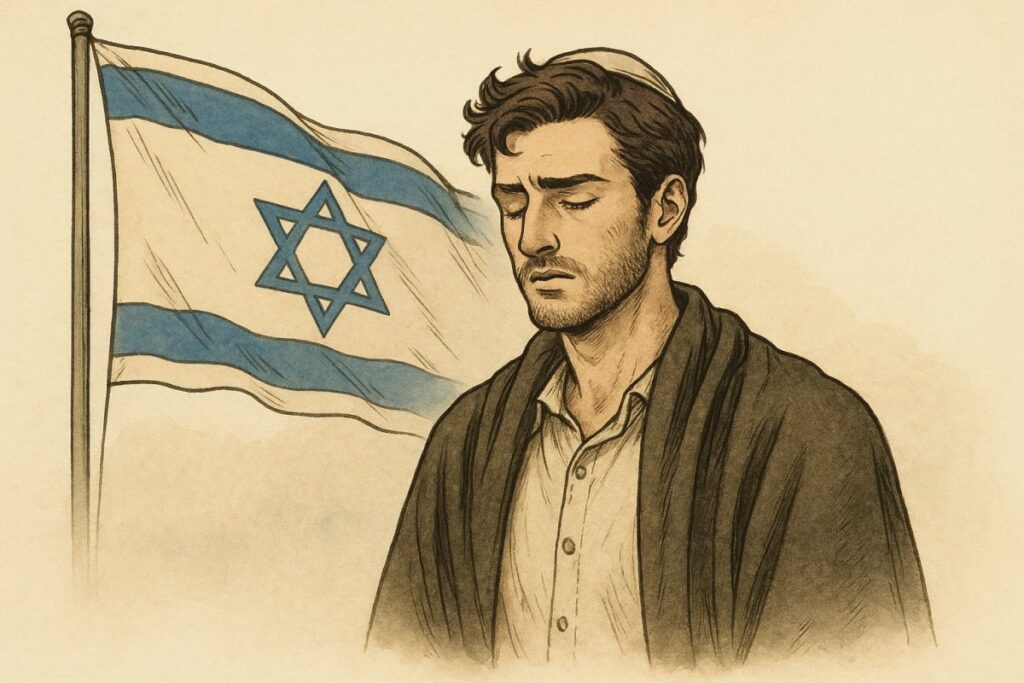
タイトルである「ハティクヴァ」は、ヘブライ語で「希望(The Hope)」を意味します。
しかし、ここで語られる希望とは、単に明るい未来を夢見ることではありません。
歌詞にある「2000年の希望」とは、ローマ帝国によって国を追われた西暦70年頃から、1948年の建国に至るまでの長い離散(ディアスポラ)の期間を指しています。
国を持たず、世界中に散らばり、多くの迫害を受けながらも、「いつか故郷へ帰る」という想いだけを頼りに民族のアイデンティティを保ち続けてきました。
その執念とも言える精神性が、この「希望」という言葉には凝縮されています。
つまり、ハティクヴァにおける希望とは、絶望の淵に立たされたとしても決して消えることのない、生存への意志そのものと言えるでしょう。
この文脈を理解することで、曲の聴こえ方は劇的に変わってくるはずです。
国歌が怖いと感じる短調の理由
「イスラエルの国歌」を調べると「怖い」という言葉が出てくることがあります。
これには音楽的な理由と歴史的な理由の双方が関係しています。
まず、音楽的に見ると、ハティクヴァは多くの国歌が高揚感のある長調(メジャーキー)であるのに対し、哀愁を帯びた短調(マイナーキー)で構成されています。
短調の旋律は、人間の心理に悲しみや不安、あるいは深刻さを想起させる効果があります。
しかし、それ以上に「怖さ」を感じさせるのは、この曲が背負っている歴史の重みかもしれません。
ホロコーストの最中、ガス室へ向かう人々が最期にこの歌を口ずさんだという記録も残されています。
死と隣り合わせの極限状態で歌われた「希望」の歌には、怨念にも似た凄まじいエネルギーが宿っていると考えられます。
単なる暗い曲というだけでなく、そこにある歴史的な「念」のようなものを、私たちは無意識に感じ取っているのかもしれません。
ユダヤ人の魂を歌う背景
歌詞の中に登場する「ユダヤ人の魂(Nefesh Yehudi)」というフレーズは、この国歌の核心部分であり、同時に現代における最大の議論の種でもあります。
この言葉は、イスラエルという国家が「ユダヤ人のための国家」であることを明確に宣言しているからです。
建国以前のシオニズム運動の文脈では、この表現は離散した同胞を団結させるための強力なスローガンでした。
しかし、多民族が共生する現代の国家において、特定の民族の「魂」のみを国歌で強調することは、そこに含まれない人々を疎外することにつながります。
それでもなお、この歌詞が変更されずに歌い継がれている背景には、ユダヤ人が歴史的に味わってきた「国を持たないことへの恐怖」と、自らのアイデンティティを守り抜こうとする強い意志が存在していると言えるでしょう。
イスラエル国歌とモルダウの類似性

ハティクヴァを聴いて「あれ、このメロディ知ってる」と感じた方の多くは、ベドルジハ・スメタナの交響詩『わが祖国』の第2曲「モルダウ(Vltava)」を連想したのではないでしょうか。
ここでは、なぜこれほどまでにメロディが似ているのか、その真相と現代におけるハティクヴァを取り巻く状況について解説します。
スメタナのモルダウに似ている真実
結論から申し上げますと、ハティクヴァは「モルダウ」の盗作ではありません。
また、スメタナがハティクヴァを真似たわけでもありません。
両者は「兄弟」のような関係にあると言えます。
実は、ハティクヴァのメロディの元となったのは、作曲者サミュエル・コーエンが幼少期に耳にしていたルーマニア民謡「牛車(Carul cu boi)」でした。
一方、スメタナもまた、自身の故郷ボヘミア地方に伝わる民謡や、スウェーデン民謡などを素材として「モルダウ」を作曲しました。
そして、これらの民謡のルーツをたどっていくと、16世紀から17世紀にかけてヨーロッパ全土で流行したある一つの旋律に行き着くのです。
つまり、両者ともヨーロッパの古い音楽的遺産という共通の「源流」から水を汲み上げ、それぞれのナショナリズムを表現するために再構築したというわけです。
メロディの起源と音楽的な系譜
その共通の源流とされるのが、ルネサンス期イタリアの楽曲「ラ・マントヴァーナ(La Mantovana)」です。
「マントヴァの舞曲」としても知られるこの旋律は、非常にキャッチーで覚えやすかったためか、国境を越えてヨーロッパ中に広まりました。
イタリアから東欧、北欧へと旅をする中で、各地の文化に合わせて少しずつ形を変え、それぞれの土地の民謡として定着していったのです。
ユダヤ人もまた、歴史の中でヨーロッパ中を移動してきた民です。
彼らが建国のために選んだ歌が、特定の土地に縛られず、ヨーロッパ中を旅してきた「彷徨えるメロディ」をベースにしているというのは、なんとも象徴的な巡り合わせだと言えるでしょう。
音楽学的にも、この旋律の系譜は非常に興味深いトピックの一つです。
パリ五輪でのブーイング騒動
国歌は時に、政治的な対立の標的となります。
記憶に新しいところでは、2024年のパリオリンピックにおいて、イスラエル代表チームの試合前にハティクヴァが流れた際、観客席から大きなブーイングが浴びせられるという事態が発生しました。
これは、当時のガザ地区における紛争や人道的な危機に対する国際的な批判が、スポーツの場に持ち込まれた結果です。
国歌斉唱は、その国の正当性や存在を認める儀式でもあります。
そのため、イスラエルの政策に反対する人々にとって、ハティクヴァを拒絶することは、政治的な意思表示の手段となるのです。
平和の祭典であるはずのオリンピックで、国歌がかき消されるほどのブーイングが起きた事実は、この曲が背負う現実の厳しさを世界に突きつけました。
アラブ系市民と国歌斉唱の論争
国際的な場だけでなく、イスラエル国内においてもハティクヴァは複雑な問題を抱えています。
イスラエルの人口の約2割はアラブ系市民(パレスチナ人など)が占めていますが、彼らにとって「ユダヤ人の魂」や「シオンへの憧れ」を歌うこの国歌は、自らのアイデンティティと相容れないものです。
過去には、アラブ系の閣僚や最高裁判事が、公式行事での国歌斉唱中に沈黙を守り、それが右派政治家からの批判を招くという論争も起きました。
「私は法律を尊重して起立はするが、歌詞の内容は私の心情を表していない」という彼らの主張は、ユダヤ国家としての性格と民主主義国家としての平等の間で揺れ動く、イスラエルの矛盾を浮き彫りにしています。
イスラエル国歌が象徴する未来
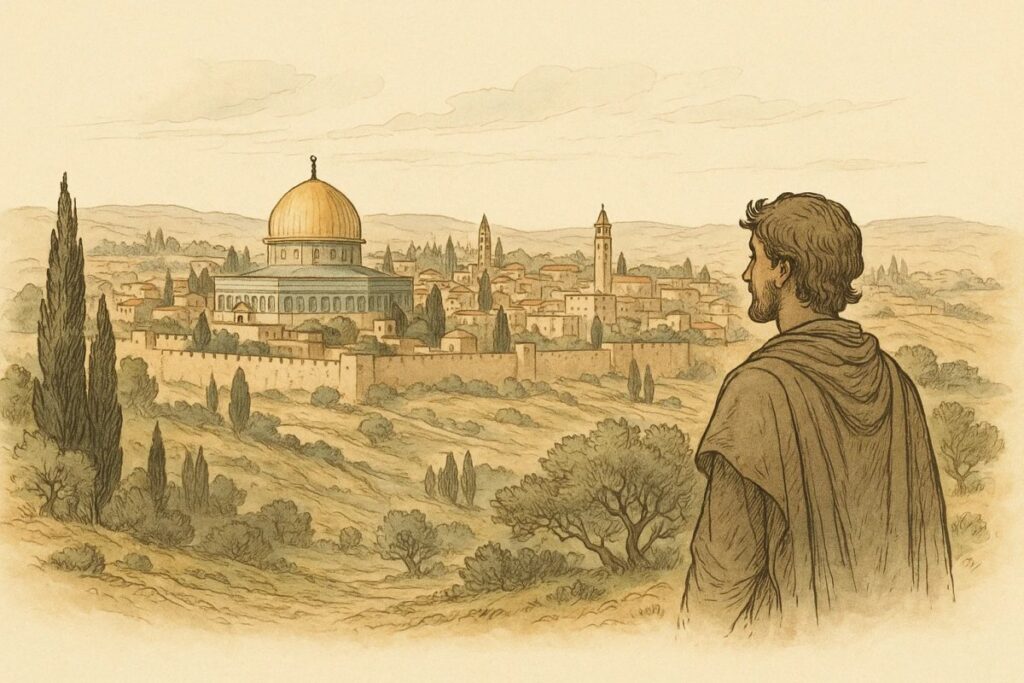
これまで見てきたように、ハティクヴァは単なる一国の歌ではありません。
それは2000年の苦難を乗り越えたユダヤ人の「希望」の結晶であると同時に、解決されていないパレスチナ問題や多文化共生の課題を映し出す鏡でもあります。
「イスラエルの国歌」というキーワードには、過去の歴史への畏敬の念と、現在の政治的な緊張感が同居しています。
この歌が将来、すべての市民にとっての希望の歌となるのか、それとも分断の象徴であり続けるのか。
その行方は、イスラエルという国家が今後どのような道を歩むのかという問いそのものと直結していると言えるでしょう。
本記事で紹介した歴史的背景や解釈は一般的な説に基づくものです。政治的な事象に関する見解は多岐にわたり、状況は常に変化しています。正確な情報については、公的な資料や専門家の分析も合わせてご参照ください。