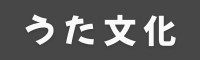「君が代」という曲を耳にしたとき、どこか不思議な感覚を覚えたことはないでしょうか。
卒業式やスポーツの国際大会で流れるこの国歌は、明るいマーチ調の他国のアンセムとは異なり、独特の静けさと重みを持っています。
- 君が代の作者はいったい誰なのか?
- 歌詞にはどんな意味が込められているのか?
- いつの時代に作られたものなのか?
こうした疑問を持つ方は少なくありません。
結論から言うと、「君が代」の“作者”は一人に決めにくいのが実情です。
歌詞は平安期の和歌(作者不詳)に由来し、明治初期にフェントンが最初の曲を作り、現在の旋律は宮内省雅楽課で形になり、和声づけ(オーケストラで荘厳に鳴る響き)で完成度が上がりました。
なお、現在の歌詞と楽曲(法令上の別記)は法律で示されています。
実は、この短い楽曲の背後には、たった一人の天才作曲家が存在するわけではありません。
千年前に詠まれた和歌、明治維新の混乱、そして西洋と日本の音楽理論の衝突――これらが複雑に絡み合い、長い時間をかけて今の形になったといえます。
ここでは、教科書的な説明だけでは見えてこない、君が代の成立に関わった「4つの主体」にスポットを当てて、その歴史を紐解いていきます。
- 歌詞のルーツが平安時代の和歌集にあること
- 最初に作曲を試みたのがイギリス人だったという事実
- 教科書に載る作者名と実質的な作曲者が異なる理由
- 独特の「和声」を生み出したドイツ人音楽家の工夫
年代の流れをつかむと、「誰が何を担ったのか」が整理しやすくなります。
| 時期(目安) | 何が起きたか | 関わった主体 |
|---|---|---|
| 平安時代前期(10世紀初頭) | 歌詞の原型となる和歌が成立 | 読み人知らず(歌詞) |
| 明治初期 | 最初の曲(初代)が作られる | フェントン(作曲) |
| 明治13年(1880年) | 現在につながる旋律が整う | 宮内省雅楽課(林広守・奥好義) |
| 明治期 | 西洋和声で式典向けに整う | エッケルト(編曲) |
君が代の作者と歌詞のルーツを解明

私たちが知っている「君が代」は、ある日突然完成したものではありません。
まずは、あの独特な歌詞がどこから来て、どのように国歌としての地位を確立していったのか、その源流から明治初期の動きまでを整理してみましょう。
歌詞の作者は古今和歌集の読み人知らず
君が代の歌詞の起源を辿ると、明治時代どころか、平安時代前期まで遡ることになります。
具体的には、延喜5年(905年)頃に編纂された『古今和歌集』の巻七「賀歌(がのうた)」に収められている一首が原典であるというのが定説です。
注目したいのは、この歌の作者が「読人(よみびと)しらず」、つまり匿名とされている点です。
特定の歌人が作った作品というよりは、当時すでに広く知られていたお祝いの歌、あるいは民謡のような存在だったと考えるのが自然でしょう。
また、原典では「君が代は」ではなく「我が君は」という歌い出しだったことが確認されています。
「我が君」という言葉は、必ずしも天皇のみを指すものではなく、親しい主君や長寿を願う身近な相手を指す言葉として使われていたようです。
これが長い伝承の中で変化し、より広い対象を祝う言葉として定着していったと考えられます。
歌い出しが「我が君は」から「君が代は」へ移っていく過程には写本や流布の影響があると整理されることが多く、どこで完全に置き換わったかは単純に一つに決めにくい点も押さえておくと、誤解が減ります。
さざれ石の意味と歌詞の元となった和歌
歌詞の中に登場する「さざれ石」や「巌(いわお)」という言葉には、どのようなイメージが込められているのでしょうか。
「さざれ石」とは「細石」、つまり小さな石のことを指します。
この歌詞は、「小さな石が長い時間をかけて成長し、大きな岩となり、さらにその表面に苔が生えるまで」という、途方もない時間の経過を表現していると解釈できます。
現代の地質学的な常識とは異なりますが、古代の伝説や信仰の中では「石は成長して岩になる」と信じられていた地域があったようです。
この表現は、単なる長寿の願いを超えて、組織や共同体が永遠に続いてほしいという「予祝(あらかじめ祝うこと)」の意味合いが強いといえます。
「さざれ石」は、現代では「小石が長い時間を経て一つの岩のように固まる(礫が結合する)」イメージで説明されることもあり、長期の繁栄を象徴する比喩として読まれることがあります。
実際、この歌は古くから結婚式や宴席、あるいは神社の祭礼など、おめでたい場で歌い継がれてきました。
福岡の志賀海神社や長崎の壱岐神楽など、神事の中でこの歌が詠まれる例も確認されており、人々の生活に深く根ざしていたことがうかがえます。
最初の作曲者はイギリス人のフェントン
実は、明治時代に入って最初に「君が代」に曲をつけたのは、日本人ではありませんでした。
その人物は、横浜に駐留していたイギリス歩兵隊の軍楽隊長、ジョン・ウィリアム・フェントンです。
明治維新直後、日本は外交儀礼の場で演奏できる「国歌」を持っていませんでした。
フェントンは「文明国として、儀式で演奏する国歌が必要だ」と日本の関係者に進言したといわれています。
このアドバイスを受けて、急遽国歌の制定プロジェクトが動き出すことになりました。
フェントン自身も作曲を申し出ましたが、彼が作った旋律(いわゆる「初代君が代」)は、現在私たちが耳にするものとは全く異なるものでした。
資料などから推測されるその曲調は、西洋の歌曲やワルツを思わせる軽快なもので、日本語の独特な抑揚とは必ずしもマッチしていなかったといわれています。
初代の初演日などは資料で具体的に示されることがあり、少なくとも「明治初期にフェントン作の礼式曲が存在した」点は公式機関の解説でも触れられています。
初代の曲が不採用になった歴史的背景

フェントンが作曲した初代バージョンは、しばらくの間演奏されていましたが、やがて公式の場から姿を消すことになります。
その主な理由は、「儀式にふさわしい重厚さに欠けていた」と判断されたためだといわれています。
天皇を迎える厳粛な儀式において、西洋風の軽やかなメロディは「軽すぎる」と感じられたのかもしれません。
また、日本語の歌詞が持つ5・7・5・7・7のリズムに対して、無理やり西洋の旋律を当てはめたことで、言葉の美しさが損なわれていたという指摘もあります。
今の国歌とは全く違う雰囲気に驚く人も多いようです。
結果として、明治9年(1876年)頃にこのバージョンは廃止され、改めて日本らしい旋律を作り直す必要性が叫ばれるようになりました。
「廃止」といっても一度に全国で切り替わったというより、改訂の上申や検討を経て扱いが変わっていったと整理されることがあり、時期の言い回しは資料によって幅が出やすい点に注意が必要です。
フェントン版の「君が代」は、現在でも資料として楽譜が残っており、再現演奏などでそのメロディを聴くことができます。
薩摩藩士の大山巌が選んだ歌詞の経緯

そもそも、なぜ『古今和歌集』のあの短歌が国歌の歌詞として選ばれたのでしょうか。
そこには、薩摩藩(現在の鹿児島県)出身の軍人、大山巌(おおやま・いわお)の影響が強かったとされています。
フェントンから「歌詞を用意してほしい」と頼まれた際、大山巌を中心とするメンバーが選定にあたりました。
彼らは薩摩藩士として、古くから薩摩琵琶の歌や地元の祝儀歌としてこの「君が代」の歌に親しんでいたといわれています。
自分たちにとって馴染み深く、かつ歴史的な重みもあるこの歌こそが、新しい国家の象徴にふさわしいと考えたのでしょう。
つまり、君が代の歌詞選定には、当時の明治政府内で力を持っていた薩摩藩の文化的背景が色濃く反映されているといえます。
君が代の作者とされる3人の人物の真実

フェントン版の失敗を経て、現在私たちが知るメロディが作られることになります。
ここには、公的な記録に残る名前と、実務を担った人物、そして仕上げを行った人物という、複雑な関係性が隠されています。
公式の作曲者として名を残す林広守
音楽の教科書や公式な記録を見ると、君が代の作曲者は「林広守(はやし・ひろもり)」と記述されていることが一般的です。
しかし、近年の研究では、彼が一人でメロディを考案したわけではないことがわかっています。
林広守は、旧幕府時代から続く楽家(雅楽を演奏する家系)の出身で、明治政府においては宮内省雅楽課のトップを務めていました。
当時の社会構造や「家」の制度において、組織の成果物はその責任者の名義で発表されることが通例でした。
林広守の役割は、部下が作った旋律を雅楽の様式に照らして監修し、最終的な責任者として世に送り出す「プロデューサー」や「総監督」に近い立場だったと考えられます。
もちろん、雅楽の伝統を守る彼の権威があったからこそ、この曲が正統性を持ち得たという側面は無視できません。
本当の作曲者である奥好義の隠れた功績
では、実際にあの旋律を生み出したのは誰なのでしょうか。
多くの資料が指し示す実質的な作曲者は、林広守の部下であった奥好義(おく・よしいさ)という人物です。
奥好義もまた雅楽の家に生まれましたが、彼は伝統音楽だけでなく、ピアノなどの西洋音楽も積極的に学んでいたといわれています。
いわば「和洋の音楽バイリンガル」でした。
フェントン版が「西洋の模倣」で失敗したことを教訓に、彼は日本の伝統的な音階である「壱越調(いちこつちょう)」の律旋法(りつせんぽう)をベースにして旋律を作りました。
律旋法とは、雅楽などで使われる独特の音階です。
ドレミで言う「レ」を中心とした音運びが、君が代の日本的な響きの正体といえます。
彼が考案した旋律は、雅楽の伝統を踏まえつつ、西洋楽器でも演奏可能な構造を持っていました。
旋律が整った時期として明治13年(1880年)が挙げられることが多く、宮内省雅楽課による初演もその年の行事に結び付けて説明されます。
奥好義はあくまで職務としてこの仕事にあたり、生涯自分の功績を誇示することはなかったようですが、彼こそが君が代の「音の建築家」といえるでしょう。
エッケルトの編曲が作った荘厳な響き

奥好義が作った旋律は、あくまで「単旋律(メロディラインのみ)」の状態でした。
これを吹奏楽やオーケストラで演奏できるように、和音(ハーモニー)をつけたのが、ドイツ人の音楽教師フランツ・エッケルトです。
エッケルトの仕事は、非常に難易度の高いものでした。
なぜなら、日本の伝統的な旋律は、西洋音楽の「ドレミ」のルール(長調や短調)には簡単には当てはまらないからです。
無理やり明るい和音をつければ雰囲気が壊れ、暗い和音をつければ不気味になってしまいます。
エッケルトはこの課題に対し、西洋の教会旋法などを応用し、旋律の持つ「和」の雰囲気を壊さないよう慎重に和声を構築しました。
現在、君が代が国際的な式典で演奏されても違和感がないのは、彼の高度な音楽理論と編曲技術があったからこそといえます。
君が代が怖いと感じる和声の理由とは
「君が代を聴くと、なんだか少し怖い気がする」
「暗い曲に聞こえる」
そう感じる人がいるのは、決して不思議なことではありません。
これはエッケルトがつけた和声が、西洋音楽でよくある「明るい解決(カタルシス)」を避けていることに起因していると考えられます。
一般的なマーチやポップスは、曲の終わりに「ジャーン」と安定した和音で終わることで、聴き手に安心感を与えます。
しかし、君が代の和声は、緊張感を保ったまま進行し、最後も完全にリラックスした状態にはなりません。
一方で、この解決しない響きこそが「荘厳」「神秘的」という評価に繋がっているともいえます。
この独特の浮遊感や緊張感が、神事のような厳粛さや、終わりのない永遠性を表現しているとも解釈できます。
「怖い」という印象は個人の主観によるものです。
よくある質問:君が代の作者と意味をめぐる疑問
- Q君が代の「君」は、今の日本では誰を指すのですか?
- A
歌詞の原型は広い意味での「敬愛する相手」を祝う歌として読まれることがあります。一方で、国会審議では憲法下の政府見解として「日本の繁栄と平和を祈念したもの」という趣旨が示されたことがあります。
- Q「君が代」には本当に“作者”がいないのですか?
- A
歌詞は古典和歌の「読み人知らず」で、作詞者を一人に特定しません。曲も、初代(フェントン)と現在の旋律(宮内省雅楽課)で段階があり、誰を「作者」と呼ぶかで答えが変わります。
- Q教科書の「作曲:林広守」と、奥好義の関係はどう考えればいいですか?
- A
組織の成果物が責任者名義で公表される慣行があった時代背景を踏まえる見方があります。その上で、旋律づくりの実務を奥好義が担ったと整理する資料が多い、という理解が近いでしょう。
- Qいつから法律で「国歌」と決まったのですか?
- A
国旗と国歌を定める法律は平成11年(1999年)に成立し、国歌を「君が代」としています。正確な条文と別記(歌詞・楽曲)は、必ず法令そのものを確認してください。
国会会議録検索システム『第145回国会 衆議院 内閣委員会 第12号』
複雑な歴史を持つ君が代の作者まとめ

ここまで見てきたように、「君が代の作者」を一人の人物に特定することは非常に困難です。
- 歌詞
千年前の「読み人知らず」(古今和歌集) - 選定
大山巌ら薩摩藩出身者 - 名義
林広守(当時の組織のトップ) - 旋律
奥好義(実質的な作曲者) - 和声
フランツ・エッケルト(西洋音楽として完成させた人物)
これら4つの異なる力が、明治という激動の時代の中で奇跡的に組み合わさって生まれたのが、現在の「君が代」だといえます。
一人の天才が作った作品ではなく、歴史の中で多くの人々が関わり、磨き上げられてきた「文化の結晶」として聴いてみると、また違った響きが感じられるかもしれません。