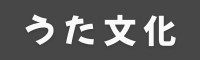運動会や選挙の出陣式などで耳にする「えいえいおー」という掛け声ですが、その本来の意味や語源について詳しく知らないという方は多いかもしれません。
先に要点だけまとめると、現代の「えいえいおー」は「団結の合図」として定着している一方、語源や漢字表記は複数の説があり、史料で確定しきれない部分も残ります。
ただの気合いを入れるための叫び声だと思われがちですが、実は戦国時代から続く歴史があると紹介されることがあり、漢字表記や英語での表現についても興味深い背景が存在します。
どの説に立つかでニュアンスが少し変わるため、「何を確認したい掛け声なのか(統率か、士気か)」という観点で読むと理解しやすくなります。
この記事では、「えいえいおー 意味」と検索された方が疑問に思うであろう漢字の由来や、いつから使われているのかという歴史、さらには現代における心理的な効果まで、幅広く整理してご紹介します。
- 「えいえいおー」に当てられる3つの漢字表記とその意味
- 戦国時代における「鬨(とき)の声」としての役割と作法
- 英語圏での類似表現や海外ドラマでの描かれ方
- 現代の運動会やビジネスシーンで期待される心理的効果
意外と知らないえいえいおーの意味と語源

普段何気なく使っている「えいえいおー」ですが、その起源を探ると、戦国時代の武士たちが命がけの戦いに挑む際の作法に行き着く、という説明がよく見られます。
ここでは、一般的に語られる漢字表記の説や、歴史的な背景について整理します。
なお、掛け声は本来「音声」として伝わるため、後から漢字を当てた可能性(当て字)も含めて考える必要があります。
えいえいおーの漢字表記は「曳々応」か
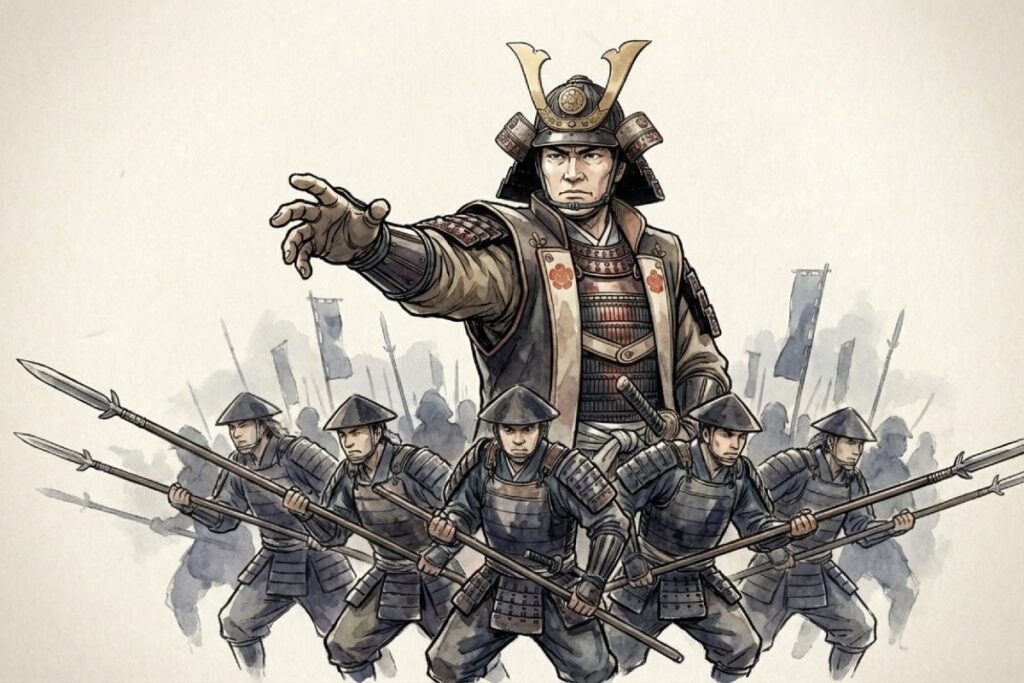
この掛け声を漢字で書く際、最も有力な説の一つとして紹介されるのが「曳々応」という表記です。
一見すると難しい字面ですが、それぞれの文字には役割分担のような意味が込められていると考えられます。
ただし、この表記自体が当時から一般化していたと断定できるわけではなく、「意味の説明として分かりやすい当て方」として流通している面もあります。
まず「曳(エイ)」という字ですが、これは「牽引する」「引っ張る」といった意味を持つ言葉です。
つまり、集団を率いるリーダー(大将)が「私は皆を引っ張っていくぞ」「進むぞ」と呼びかける合図として機能していたと解釈できます。
これに対し、「応(オー)」は「反応する」「応える」という意味を持ちます。
大将の呼びかけに対して、兵士たちが「応じます」「従います」と声を返すわけです。
このような「呼びかけ(Call)→呼応(Response)」の構造は、現代のコール&レスポンスにも近く、集団の足並みをそろえる実用性があったと考える余地があります。
このように考えると、「えいえいおー」は単なる叫び声ではなく、リーダーとメンバーの間で交わされる「統率と服従の確認儀式」であったといえそうです。
「曳々応」説では、大将の「曳(Call)」と兵士の「応(Response)」による対話構造になっていると解釈されます。
語源とされる上杉謙信と戦国時代
この「曳々応」という言葉の由来としてよく挙げられるのが、戦国大名の上杉謙信です。
軍学書である『北越軍談』などの文献には、上杉軍の軍法や作法に関する記述があり、その中にこの掛け声の原型が見られるといわれています。
『北越軍談』が収録資料として扱われている例としては、国立国会図書館の所蔵資料情報でも確認できます。
戦国時代において、軍の統率は生死を分ける重要な要素でした。
数千、数万という兵士を一斉に動かすためには、太鼓や法螺貝(ほらがい)だけでなく、肉声による確認作業も必要だったのでしょう。
上杉謙信のようなカリスマ性のある武将が、この掛け声を通じて軍全体の意思統一を図っていた光景が想像されます。
ただし、これらの文献が書かれたのは戦国時代そのものよりも後の江戸時代であることも多く、記述内容がすべて当時の事実そのままであるとは限りません。
あくまで、後世の軍学者が「理想的な軍隊統率のあり方」として体系化したものという側面もある点は留意が必要です。
鋭々応説やチコちゃんでの解説内容
もう一つ、近年テレビ番組『チコちゃんに叱られる!』などで取り上げられ話題となったのが「鋭々応」という漢字表記説です。
読み方は同じですが、込められた意味合いが少し異なります。
こちらの説では、「エイ」の部分に「鋭」という字を当てます。
「鋭」には「鋭い」「精鋭」「鋭気」といった意味が含まれます。
つまり、大将が「我々の気力は充実しているか」「お前たちは精鋭か」と問いかけ、それに対して兵士たちが応えるという解釈になります。
「曳々応」が統率の仕組みを説明するのに対し、「鋭々応」は士気の状態を言語化した説明として理解しやすい、という違いもあります。
「曳」が物理的な統率や進行方向を示すのに対し、「鋭」は兵士たちの士気や精神状態(コンディション)を確認するニュアンスが強いといえます。
戦いに臨むにあたり、自分たちが強い兵士であると再確認することは、恐怖心を打ち払うためにも有効だったと考えられます。
他にも「叡王(えいおう)」と書き、戦神や不動明王などへの祈願を込めていたとする説も存在します。
勝どきや鬨の声との違いを詳しく解説

歴史ドラマなどで「勝どきを上げろ!」というセリフを聞くことがありますが、「えいえいおー」は厳密には「勝どき」とは異なる場面で使われることがあったようです。
ここでは「鬨(とき)の声」という大きな枠組みの中で整理してみます。
一般的に、戦いの前に行うのが「鬨の声(Battle Cry)」であり、戦いに勝った後に行うのが「勝どき(Victory Cry)」と区別して説明されることがあります。
図書館レファレンスの事例では、戦国期の作法として「総大将が『えい、えい』と声を出し、兵が『おう』と呼応する」といった説明も紹介されています。
レファレンス協同データベース「『鯨波(げいは)の声』と『エイ・エイ・オー』について」
「えいえいおー」は、本来はこれから戦場に向かう際に士気を高め、敵を威圧するための「開戦前の儀式」としての性格が強かったといわれています。
また、数千人の兵士が一斉に叫ぶ声は、しばしば「鯨波(げいは)」と表現されます。
これは鯨が波を打つ音や、荒れ狂う波の轟音に例えたもので、当時の鬨の声がどれほど凄まじい迫力を持っていたかを物語っています。
現代の運動会のような明るい雰囲気とは異なり、かつてはもっと威圧的で腹の底に響くようなものだったのかもしれません。
現代でも「勝った後」にも「これからやるぞ」にも同じ掛け声が使われることがありますが、これは本来の用語上の区別が日常の場面では優先されにくいため、と考えると整理しやすいでしょう。
えいえいおーはいつから使われたか

では、この掛け声は具体的にいつから使われているのでしょうか。
前述のように戦国時代の軍記物に記述が見られることから、少なくとも中世後期には原型となる習慣が存在していたと考えられます。
一方で、「鬨の声」そのものはさらに古い時代から言及があるとされ、用語や作法が時代ごとに変化しながら受け継がれてきた可能性もあります。
しかし、それが現在のような形で一般庶民にまで広まったのは、明治時代以降であるという見方が一般的です。
明治維新によって武士階級がなくなり、西洋式の軍隊教育や学校教育が導入される過程で、集団行動を統率するための号令として「えいえいおー」が転用された可能性があります。
特に、学校での運動会や体育教育を通じて子どもたちに浸透したことが、現代までこの言葉が廃れずに残った大きな要因の一つといえるでしょう。
かつての「死の覚悟」の言葉が、平和な時代の「団結の合図」へと意味を変えながら受け継がれてきた歴史の流れを感じます。
英語や現代社会でのえいえいおーの意味

時代とともに役割を変えてきた「えいえいおー」ですが、現代では日本独自の文化として、またビジネスやエンターテインメントの要素として機能しています。
ここでは海外の言葉との比較や、現代社会での使われ方について深掘りします。
えいえいおーを英語に翻訳すると
「えいえいおー」を英語で表現する場合、文脈によって適切な言葉が変わります。
最も一般的によく使われる翻訳は “Hip hip hooray” です。
これは誰かを称える時や、お祝いの場面で使われるフレーズで、音のリズムも似ています。
ただし、英語圏では「日本語の掛け声」をそのまま置き換えられる定番訳が常にあるわけではないため、何の場面かを優先して選ぶのが実用的です。
文脈別の目安を、一般的な例としてまとめると次のようになります(あくまで目安で、正確な言い回しは場面や相手に合わせて調整してください)。
| 近い場面 | 伝えたいニュアンス | 英語表現の例 |
|---|---|---|
| 試合や発表の直前 | これから行くぞ | “Let’s go!” |
| 困難に挑む前 | できるはずだ | “We can do it!” |
| 応援・鼓舞 | がんばれ | “Go for it!” |
| お祝い・称賛 | 万歳・歓声 | “Hip hip hooray!” |
しかし、これから戦いや試合に臨むという「決意表明」のニュアンスを重視する場合は、”Let’s go!” や “We can do it!” といった言葉の方が近いかもしれません。
また、軍事的な士気高揚という意味では、アメリカ海兵隊の “Oorah!”(ウーラー)などが精神的に近いものといえます。
ただし、これは特定組織の掛け声としての背景を持つため、一般会話で安易に転用するより、場面の近い中立的な表現を選ぶ方が誤解は起きにくいでしょう。
“Battle Cry” と直訳することも可能ですが、日常会話で使うには少し大げさで攻撃的な響きになる場合があります。
運動会や選挙での使い方と心理効果

現代日本において、「えいえいおー」が最も象徴的に使われるのは運動会と選挙です。
運動会では、紅組・白組に分かれて声を出すことで、チームとしての一体感を高める効果があります。
心理学的には、大きな声を出したり、拳を突き上げる動作(身体的同期)を行うことで、集団への帰属意識が高まり、やる気スイッチが入る「プライミング効果」が期待できるといわれています。
ただし、効果の大きさは状況や個人差にも左右されやすく、声をそろえる行為が「必ず」高い成果につながるとまでは言い切れません。
選挙の出陣式でも同様に、候補者と支援者が結束を確認するために行われます。
ここでは「戦いに出る」という戦国時代からのメタファーが色濃く残っており、昔ながらの「えいえいおー」が好まれる傾向にあります。
近年では「ガンバローコール」も一般的ですが、より重厚感や伝統を重んじる場面では、今でも「えいえいおー」が選ばれることが多いようです。
海外ドラマSHOGUNでの描かれ方
日本文化への関心が高まる中、海外ドラマ『SHOGUN 将軍』などの作品を通じて、この掛け声が世界に知られる機会も増えています。
劇中でサムライたちが「エイ!エイ!オー!」と叫ぶシーンは、海外の視聴者に強烈な印象を与えました。
しかし、英語字幕では具体的な言葉として翻訳されず、単に「(Samurai chanting)」や「(Samurai cheering)」と表記されるケースもあったようです。
これにより、海外のファンからは「彼らは具体的に何と言っているのか?」「どんな意味があるのか?」といった疑問の声が上がり、検索需要が生まれる一因ともなりました。
言葉の響きそのものが持つ力強さは、字幕を超えて伝わっているといえそうです。
洋楽Zombieの歌詞との関連性は
アイルランドのロックバンド、The Cranberries(クランベリーズ)の世界的ヒット曲『Zombie』の歌詞に、「ei, ei, oh」と聞こえるフレーズが登場します。
これにより、「この曲の歌詞は日本の掛け声と関係があるのか?」と疑問を持つ方もいるようです。
実際には、歌詞がそう聞こえる(または「zombie-ie-ie」のように表記されることが多い)ために連想が生まれた、という受け止め方が近いでしょう。
結論から言えば、これは偶然の一致であると考えられます。
歌詞の文脈では、苦悩や嘆き、あるいは叫びを表現する音声的なパフォーマンスとして歌われており、日本の戦国時代の掛け声とは語源的な繋がりはないと見るのが自然です。
とはいえ、言葉の通じない国同士でも、力を込めたり感情を吐き出したりする際の音が似通うというのは興味深い現象です。
意味は違えど、音の響きに原始的な共通点があるのかもしれません。
よくある質問:えいえいおーの意味・漢字・英語
- Q「えいえいおー」に正式な漢字表記はありますか?
- A
「曳々応」「鋭々応」などの表記は説として紹介されますが、どれか一つが公式に確定しているとは限りません。場面説明として当て字が広まっている可能性もあるため、迷うならひらがな表記が無難です。
- Q「えいえいおー」は必ず3回繰り返すものですか?
- A
3回繰り返す形が定着している場面は多いものの、地域・学校・団体の慣習で回数や言い方が変わることがあります。式典などで不安なら、事前に主催側の進行に合わせるのが確実です。
- Q英語では結局どれを言えばいいですか?
- A
お祝いなら “Hip hip hooray”、これから頑張るなら “Let’s go!” や “We can do it!” が目安です。正確な言い回しは相手や状況で変わるので、直訳より「場面」を優先すると伝わりやすくなります。
- Q「鬨の声」「勝どき」と「えいえいおー」は同じですか?
- A
一般には、戦いの前を「鬨の声」、勝った後を「勝どき」と区別して説明されます。現代では両方の意味が混ざって使われることも多く、用語上の区別が日常で必ず守られるわけではありません。
えいえいおーの意味と歴史のまとめ
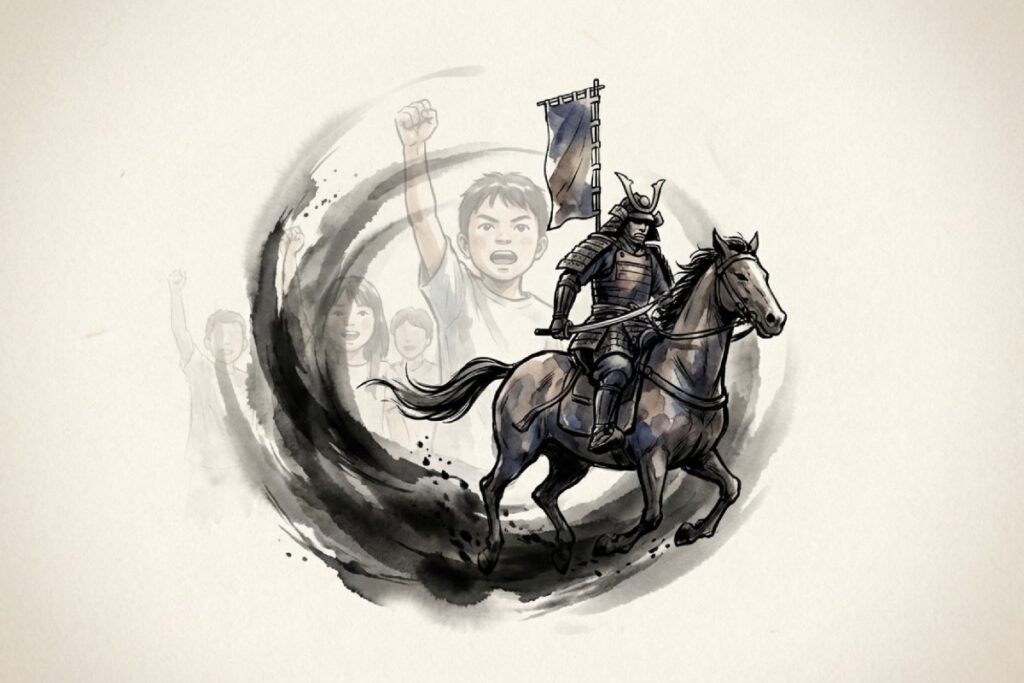
「えいえいおー 意味」について調べてみると、単なる元気な掛け声というだけでなく、リーダーとメンバーが心を一つにするための歴史ある「儀式」であることが分かってきました。
- 曳々応
指揮官が引き、兵士が応えるという統率の確認 - 鋭々応
自分たちが精鋭であることを鼓舞する士気高揚 - 変遷
戦国時代の鬨の声から、現代の運動会や選挙まで形を変えて継承 - 機能
集団の同調性を高め、スイッチを入れる心理的装置
集団の気持ちをそろえる手段は、掛け声に限らず時代ごとに姿を変えてきました。音楽の力やリズムの同期が人の心理に与える影響も、合わせて見ておくと理解が深まります。
時代が変わっても、人が集まって何か大きな目標に向かう時、声を合わせて気持ちを揃えるという行為の重要性は変わらないのかもしれません。
次にこの掛け声を耳にした時は、その背後にある歴史や意味に少し思いを馳せてみてはいかがでしょうか。