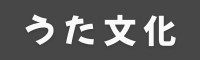音楽理論を学ぶ上で欠かせない属七の和音ですが、初めて学ぶ人にとっては少し難しく感じるかもしれません。この記事では、属七の和音をわかりやすく解説していきます。
音楽理論におけるコードの理解を深めるために、この記事を参考にしながら学んでいきましょう。
- 属七の和音とは何か、基本的な構造と意味を理解できる
- 属七の和音の特徴や、和音進行における役割を学べる
- ハ長調など具体的な例で、属七の和音の書き方やコードネームがわかる
- 減七の和音や転回、省略といった応用的な内容を把握できる
属七の和音をわかりやすく学ぶ

- 属七の和音とは?
- どういう意味?
- 特徴は?
- ハ長調では?
- コードネーム
- 属七の和音 一覧表
属七の和音とは?
属七の和音は、西洋音楽において非常に重要な役割を持つ和音の一つです。具体的には、音階の5番目の音(属音)を基に作られる四和音のことを指します。この和音は、音楽の流れの中で不安定な響きを持ち、次の和音へと進む力が強いため、主に和音進行の中で使用されます。
属七の和音は、三和音の上にもう一つ音を加えた四和音です。
例えば、ト長調であれば「レ・ファ#・ラ・ド」が属七の和音となります。この構成により、特に強い解決力を持ち、主和音(I)などへ自然に進む流れを作り出す特徴があります。

この和音の特徴は、三全音(トライトーン)と呼ばれる非常に不安定な響きを持つ点です。この不安定さが、属七の和音を音楽的に次の和音へ導く役割を果たしています。そのため、コード進行では必ずと言ってよいほど登場する、極めて重要な存在です。
どういう意味?
「属七」とは、音階の5番目の音(属音)を基に作られた七の和音(四和音)のことを指します。「属」はその音階の中での「属音」を意味し、「七」はその和音が四つの異なる音である
根音、3度、5度、7度
で構成されていることを示しています。
この「七」という表現は、音程の上で「根音」から「第7音」までの間に「短7度」という関係があるためです。つまり、「属七」という名前は、音楽理論上の音階構造と、その和音が持つ解決性を指す言葉として使われています。この和音は、特に他の和音へ進む際に強い力を発揮し、音楽の調を確立する上で不可欠な要素となります。
特徴は?
属七の和音の最大の特徴は、音楽における「不安定さ」と「解決力」です。この和音は、三和音にさらに音を加えた四和音であり、特に次の和音へと進もうとする強い力を持っています。属七の和音を使うことで、和音進行に緊張感を与え、その後に続く和音にスムーズに移行できるため、楽曲全体に流れや方向性が生まれます。
具体的には、属七の和音は根音、第3音、第5音、そして第7音から成り立っています。これにより、三全音(トライトーン)と呼ばれる音程が生じ、この音程が不安定な響きを生み出します。この不安定さが、音楽に「次に進むべき」という強い緊張感を生じさせ、最終的に主和音に解決されることで音楽が安定します。
また、属七の和音は、長調と短調の両方で同じ役割を果たしますが、音程の違いによって微妙な響きの変化が生じます。長調ではより明るく力強い響き、短調ではやや暗く落ち着いた響きが感じられるのも特徴の一つです。
ハ長調では?
ハ長調における属七の和音は、「ソ・シ・レ・ファ」の4つの音で構成されます。ハ長調の音階で5番目の音である「ソ」を根音として、この上に第3音「シ」、第5音「レ」、そして第7音「ファ」が加わることで、典型的な属七の和音が完成します。

この和音は、次に主和音である「ド・ミ・ソ」(Cメジャー)へと解決する力が非常に強く、調性を明確にする重要な役割を担います。例えば、楽曲の終わりにこの「ソ・シ・レ・ファ」の和音を用いることで、ハ長調の楽曲を締めくくる効果的な和音進行が実現します。
また、ハ長調の属七の和音は、クラシック音楽だけでなくポップスやジャズなどさまざまな音楽ジャンルでも頻繁に使用されます。この和音が生み出す解決感は、聴く人に「曲が完結する」という安心感を与え、音楽的な構成において欠かせない存在です。
コードネーム
属七の和音のコードネームは、一般的に「V7」と表記されます。この「V」はルート音(根音)を示し、例えばハ長調の属七の和音であれば「G7」となります。属七の和音は、根音(V)に長三度、完全五度、短七度を加えた形で成り立っているため、ルート音に「7」を付ける形でコードを表現します。
このコードネームは、ポピュラー音楽、ジャズ、ロックなど、幅広いジャンルで使用されており、楽譜やコード進行を簡潔に伝えるために非常に便利です。たとえば、楽譜上で「C7」と書かれていれば、C(ド)を根音とし、ミ、ソ、シ♭という音を重ねた属七の和音を意味します。コードネームはシンプルながら、音楽の進行や響きを瞬時に理解させるために欠かせないものです。

属七の和音は、解決感を伴う強い進行を持つため、曲の流れをスムーズにする役割を担います。このため、楽曲内でよく見られる「G7→C」のような進行は、音楽の調性を強調する重要な役割を果たしています。
属七の和音 一覧表
属七の和音は、音楽理論において非常に重要な和音であり、和音進行の中で調性を明確にする役割を果たします。ここでは、属七の和音について、各調ごとの具体的な例を示しながら、その構造をわかりやすく整理します。
属七の和音は、音階の5番目の音(属音)を根音として、そこから長三度、完全五度、そして短七度の音を積み重ねた四和音です。これにより、非常に強い解決力を持つ和音が形成され、特に主和音に向かう際に使用されます。
以下に、すべての調における属七の和音の構成音を一覧にまとめました。
| 調 | 属七の和音 |
|---|---|
| ハ長調(C) | ソ・シ・レ・ファ |
| 嬰ハ長調(C#) | ソ♯・シ♯・レ♯・ファ♯ |
| ニ長調(D) | ラ・ド♯・ミ・ソ |
| 変ホ長調(E♭) | シ♭・レ・ファ・ラ♭ |
| ホ長調(E) | シ・レ♯・ファ♯・ラ |
| ヘ長調(F) | ド・ミ・ソ・シ♭ |
| 嬰ヘ長調(F#) | ド♯・ミ♯・ソ♯・シ |
| ト長調(G) | レ・ファ♯・ラ・ド |
| 変イ長調(A♭) | ミ♭・ソ・シ♭・レ♭ |
| イ長調(A) | ミ・ソ♯・シ・レ |
| 変ロ長調(B♭) | ファ・ラ・ド・ミ♭ |
| ロ長調(B) | ファ♯・ラ♯・ド♯・ミ |
属七の和音は、曲の流れを滑らかにし、調性を明確にする重要な役割を担っています。また、転回形や省略形も存在し、音楽の流れや構造に応じて多様な使い方ができます。
属七の和音を更にわかりやすく解説

- 書き方
- 記号で表現
- 解決方法
- 転回
- 省略
- 減七の和音とは?
- 減七の和音 一覧表
書き方
属七の和音の書き方は、基本的には和音記号「Ⅴ7」のように表記されます。これは、ローマ数字で属音を示し、その右下に小さく「7」を付け加えることで属七の和音であることを表しています。例えば、ハ長調における属七の和音は「Ⅴ7」となり、具体的な音は「ソ・シ・レ・ファ」となります。

書き方においては、転回形もよく使用されます。転回形とは、和音の構成音を順番に並べ替えて書く方法です。属七の和音の場合、第1転回形では第3音を根音にし、第2転回形では第5音を根音にする、といった形で表現されます。例えば、ハ長調の属七の和音(ソ・シ・レ・ファ)を第1転回形にすると、「シ・レ・ファ・ソ」となります。
さらに、和音記号として「Ⅴ7」と表記される際、楽譜上で細かい指示を与えることができ、転回形や省略形を用いることで、より柔軟な和音進行を実現できます。このような書き方を理解することで、楽曲の構成や演奏がスムーズに進むようになります。
記号で表現
属七の和音を表す記号は、一般的にローマ数字と「7」を組み合わせた形式で表現されます。具体的には、属七の和音は「Ⅴ7」という形で記載されます。この「Ⅴ」は音階上の5番目の音、つまり属音を意味し、右下に小さく付けられる「7」がその和音が七の和音であることを示しています。例えば、ハ長調の属七の和音であれば、「Ⅴ7」であり、これは「ソ・シ・レ・ファ」の四和音を指します。
また、コードネームで表す場合は「G7」のように記載され、ポピュラー音楽などではこの表記がよく使われます。この記号法により、和音の構造や進行が瞬時に理解できるため、楽譜を読む際や作曲・編曲を行う際に非常に便利です。
属七の和音は、その不安定な響きから次の和音への強い進行を促すため、音楽の中で調性を明確にし、スムーズな和音進行を作り出す重要な役割を果たします。
解決方法
属七の和音は、次の和音に進みたがる強い力を持っているため、必然的に解決を求めます。解決方法として最も一般的なのは、属七の和音から主和音(I)へ進行することです。例えば、ハ長調の属七の和音(G7)は「ソ・シ・レ・ファ」で構成されていますが、これが主和音である「ド・ミ・ソ」(C)に進むことで、安定した響きが得られます。

この解決のポイントは、属七の和音の中で特に不安定な音である第3音「シ」と第7音「ファ」が半音進行することです。シは主和音の根音「ド」へ、ファは主和音の第3音「ミ」へと半音で進み、音楽的に強い安定感を与えます。このような進行を「ドミナントモーション」と呼び、属七の和音の特徴的な解決方法です。
一方で、必ずしも主和音に進むだけではなく、時には別の和音へ進行する場合もありますが、基本的にはこの「Ⅴ7→Ⅰ」の進行が音楽における最も自然で力強い解決とされています。
転回
属七の和音の転回とは、和音の構成音の順番を入れ替えて、異なる音を根音(ベース音)に持ってくる手法です。通常、和音は基本形と呼ばれる形があり、例えばハ長調の属七の和音「ソ・シ・レ・ファ」では「ソ」が根音となります。しかし、転回を使うことで、この和音を別の形に変えることができ、演奏や作曲に多様な響きをもたらします。
属七の和音には3つの転回形があり、それぞれが異なる響きを持ちます。
第1転回形は第3音(シ)を根音にした「シ・レ・ファ・ソ」。

第2転回形は第5音(レ)を根音にした「レ・ファ・ソ・シ」です。

そして第3転回形は第7音(ファ)を根音にした「ファ・ソ・シ・レ」となります。

このように転回することで、和音進行の中で滑らかな音の動きが可能になり、楽曲により豊かな表現を加えることができます。
転回形を使うメリットとして、和音の重なりや響きを変えながら、同じ属七の和音を使える点が挙げられます。これにより、和音進行が単調にならず、動きのある音楽構造が作られます。
省略
属七の和音の省略とは、和音の一部を取り除きつつ、その機能を損なわずに使用する技法です。属七の和音は通常、4つの音から成り立っていますが、演奏の都合や音の密度を調整するために、特定の音を省略することがあります。
最も一般的な省略方法は、第5音を省略する形です。例えば、ハ長調の属七の和音「ソ・シ・レ・ファ」の場合、完全5度である「レ」を省略して「ソ・シ・ファ」として演奏することが可能です。このように第5音を省略しても、和音の主要な機能である緊張感や解決感は保たれるため、属七の和音としての役割を十分に果たします。
省略のメリットは、特にピアノやギターのような和音を扱う楽器で音の重なりを減らすことができる点です。また、音域の調整や他の楽器とのバランスを取る際にも有効です。しかし、音を省略しすぎると、属七の和音特有の響きが損なわれる可能性もあるため、バランスを考慮しながら省略することが重要です。
減七の和音とは?
減七の和音とは、属七の和音と同じく四和音の一種ですが、異なる特徴を持つ不協和音です。ディミニッシュコードとも呼ばれます。減七の和音は、減三和音にさらに短7度を加えたもので、非常に不安定な響きを持つ和音です。具体的には、ハ長調であれば「シ・レ・ファ・ラ♭」という音の組み合わせになります。

この和音は、非常に強い緊張感を持ち、解決を求める性質が強いため、特に次の和音に進む際に多用されます。
減七の和音の主な特徴は、全ての音が短3度間隔で構成されている点です。つまり音を転回することで、他の減七の和音に変形することができます。12音階は3つのグループに分類できます。
この構造により、同じ減七の和音が異なる転調先にも使いやすく、転調のきっかけとして頻繁に使用されます。クラシック音楽はもちろん、現代のポピュラー音楽やジャズでもこの和音は重要な役割を果たします。
ただし、減七の和音は非常に不安定なため、使用する際にはその後に必ず安定した和音へ解決することが求められます。これにより、楽曲全体の流れがスムーズに進行し、和音の緊張感が解消される効果が生まれます。
減七の和音 一覧表
減七の和音は、不安定な響きと解決感を持つ、音楽の中で重要な役割を果たす四和音です。減七の和音は、短3度を積み重ねた音程構成で、強い緊張感を生み出します。音楽の進行において、減七の和音は他の和音に進むための橋渡しのような存在であり、特に転調や次の和音への移行に効果的です。
以下は、すべての調における減七の和音の一覧です。各調において、減七の和音は同じような音程関係を保ちつつ、異なる音を構成音に持っています。
| 調 | 減七の和音 |
|---|---|
| ハ長調(C) | シ・レ・ファ・ラ♭ |
| 嬰ハ長調(C#) | シ♯・レ♯・ファ♯・ラ |
| ニ長調(D) | ド♯・ミ・ソ・シ♭ |
| 変ホ長調(E♭) | レ・ファ・ラ♭・ド♭ |
| ホ長調(E) | レ♯・ファ♯・ラ・ド |
| ヘ長調(F) | ミ・ソ・シ♭・レ♭ |
| 嬰ヘ長調(F#) | ミ♯・ソ♯・シ・レ |
| ト長調(G) | ファ♯・ラ・ド・ミ♭ |
| 変イ長調(A♭) | ソ・シ♭・レ♭・ミ |
| イ長調(A) | ソ♯・シ・レ・ファ |
| 変ロ長調(B♭) | ラ・ド・ミ♭・ソ♭ |
| ロ長調(B) | ラ♯・ド♯・ミ・ソ |
このように、すべての調において減七の和音は同じ短3度間隔で積み重なっています。これにより、音楽の緊張感を高め、次に続く和音への解決感を生むことができます。減七の和音は、特にクラシックやジャズの分野で多用されるため、演奏や作曲の際に理解しておくと、より豊かな音楽表現が可能になります。
記事のまとめ
- 属七の和音は音階の5番目の音を基に作られる四和音
- 不安定な響きを持ち、次の和音に進む力が強い
- 主に和音進行の中で使用される
- ハ長調の属七の和音は「ソ・シ・レ・ファ」
- 三全音(トライトーン)を含み、不安定な音程を持つ
- 属七の和音は主和音へ自然に進む性質がある
- 「属七の七」は四和音で構成された和音のことを示す
- コードネームでは「G7」のように表記される
- 属七の和音の記号は「Ⅴ7」として表される
- 属七の和音の解決方法は主和音(I)への進行が基本
- 転回形を使うことで音の並び替えが可能
- 第5音を省略しても属七の和音として機能する
- 減七の和音は不協和音で、解決を求める力が強い
- 減七の和音は全ての音が短3度間隔で構成される
- 属七の和音は長調・短調で共通の機能を持つ
- 和音進行の中で調性を確立する役割を果たす
- 転調時にも減七の和音がよく使われる
- 属七の和音はポピュラー音楽やクラシックでも多用される
- 解決により楽曲全体に安定感を与える