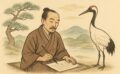多くの人が慣れ親しんだ童謡「赤とんぼ」ですが、その歌詞 内容を深く読み解くと、切なさや悲しみが感じられ、一部では赤とんぼの歌詞は怖いとさえ言われています。
この記事では、なぜ夕焼け小焼けの歌詞が怖いと感じられるのか、その背景にある真実を解き明かします。
歌詞の1番から4番までを追いながら、「負われて見た」のはどういう意味か、2番に出てくる「桑の実」の意味、そして3番で描かれる「別れ」、4番の「竿の先」が示す情景の変化までを詳細に解説します。
特に重要なのが、「姐や」と、「お里の頼りが絶え果てた」の意味です。
この歌に込められた本当のメッセージが見えてくるでしょう。
- 童謡「赤とんぼ」の歌詞に込められた本当の意味
- 歌詞に登場する「姐や」の正体と作者との関係
- 歌詞が「怖い」「切ない」と感じられる背景
- 作者三木露風の幼少期と作詞の時代背景
赤とんぼの歌詞が怖いと言われる本当の理由

- 童謡「赤とんぼ」の歌詞の内容
- 赤とんぼを「負われて見た」とは?
- 歌詞に出てくる「姐や」はどういう意味?
- 2番の歌詞にある桑の実の意味を解説
- 孤独を感じさせる3番の歌詞の内容
- お里のたよりも絶え果てたとは?
童謡「赤とんぼ」の歌詞の内容

童謡「赤とんぼ」は、作詞家である三木露風が自身の幼少期を回想して創作した作品です。
そのため、歌詞の内容を正しく理解するには、彼の生い立ちを知ることが不可欠となります。
三木露風は5歳のときに両親が離婚し、その後は母方の祖父に引き取られて育ちました。
しかし、実際に彼の日々の面倒を見ていたのは、子守りとして雇われていた一人の少女でした。
この歌は、その少女との思い出や、生き別れとなった母への思慕の念が色濃く反映された、非常に個人的な内容の作品なのです。
一見すると、美しい夕焼けの情景を歌ったノスタルジックな童謡に思えますが、その背景には幼い露風が抱えた寂しさや、会いたくても会えない母への切ない気持ちが込められています。
この美しい情景と悲しい背景の対比こそが、この歌に深い奥行きを与え、聴く者の心を揺さぶる理由と言えるでしょう。
1番の赤とんぼを「負われて見た」とは?

1番
夕焼、小焼の、あかとんぼ、負はれて見たのは、いつの日か。
歌詞の1番にある「負われて見たのはいつの日か」という一節は、この歌の解釈において最も重要な部分の一つです。
この「負われて」を、赤とんぼを「追いかけて」と誤解しているケースが少なくありません。
しかし、ここでの「負う」は「背負う」を意味します。
つまり、このフレーズは「(誰かの背中に)背負われて赤とんぼを見たのは、いったいいつの日のことだっただろうか」と、遠い過去を懐かしむ情景を描写しているのです。
三木露風自身も、後年に「姐やとあるのは子守娘のことである。私の子守娘が、私を背に負ふて広場で遊んでいた。その時、私が背の上で見たのが赤とんぼである」と書き残しています。
この一節だけで、幼い主人公が誰かに愛情深く世話をされていた、温かい記憶の断片が浮かび上がります。
追いかけるという能動的な行為ではなく、背負われるという受動的な視点から描かれている点が、主人公の幼さや、保護されていた頃の懐かしさを強調しているのです。
2番の歌詞にある桑の実の意味を解説

2番
山の畑の、桑の実を、小籠に、つんだは、まぼろしか。
2番の「山の畑の桑の実を 小かごに摘んだは まぼろしか」という部分は、姐やと過ごした日々の具体的な思い出を描写しています。
桑の実は、養蚕が盛んだった当時の日本の田園風景を象徴するアイテムです。
この一節は、姐やと一緒に桑畑へ行き、熟した黒紫色の実を小さなかごに摘んで遊んだ、楽しく平和な時間を表現しています。
しかし、文末が「まぼろしか」と結ばれている点に注意が必要です。
この言葉によって、楽しかったはずの思い出が、今となってはまるで幻のように儚く、遠い出来事であったかのように感じられます。
幸せだった過去と、それがもう戻らない現在との対比が、この「まぼろしか」という一言に凝縮されています。
姐やとの何気ない日常の一コマを具体的に描くことで、彼女を失った喪失感がより一層際立って感じられるのです。
3番の歌詞に出てくる「姐や」はどういう意味?

3番
十五で、姐やは嫁にゆき、お里の、たよりも、たえはてた。
歌詞の3番に登場する「姐や」は、実の姉のことではありません。
これは、当時、他家で子守りや家事手伝いをする若い女性を指した「子守娘(こもりむすめ)」の呼び名です。
三木露風にはそもそも姉がいなかったことからも、この「姐や」が血縁者でないことは明らかです。
露風が5歳で両親と離れた後、彼を親身に世話したのが、この姐やでした。
当時の農村では、貧しい家庭が生活のために娘を子守り奉公に出すことは珍しくなく、口減らしという側面もありました。
姐やは、親の愛情に触れる機会が少なかった幼い露風にとって、母親代わりのような温かい存在だったと考えられます。
| 誤解されやすい解釈 | 本来の意味 |
|---|---|
| 実の姉 | 子守り奉公の少女 |
| 血縁関係にある親族 | 血縁関係のない他人 |
このように、姐やが誰であるかを理解することは、歌詞全体の切ないトーンを把握する上で非常に重要です。
露風が抱く姐やへの愛情や思慕の念が、この歌の根底に流れているのです。
孤独を感じさせる3番の歌詞の内容

3番の歌詞は、この歌の物語が大きく動く転換点であり、切なさの核心に触れる部分です。
十五で姐やは嫁に行き
この一節は、姐やが15歳という若さで嫁いでいった事実を伝えています。
これは露風が15歳の時ではなく、姐やの年齢が15歳だったという意味です。
当時の結婚年齢としては決して早すぎるわけではありませんでしたが、露風にとっては、最も信頼し、慕っていた人物との突然の別れを意味しました。
母親代わりであった姐やを失った彼の孤独感は、計り知れないものがあったでしょう。
お里のたよりも絶えはてた
続くこの一節が、歌詞を一層悲しいものにしています。
これについては次の見出しで詳しく解説しますが、姐やが嫁いでしまったことで、彼女との繋がりが完全に断たれてしまった状況を示唆しています。
慕っていた人との別れと、その後の消息不明という二重の喪失が、ここで描かれているのです。
お里のたよりも絶えはてたとは?

「お里のたよりも絶えはてた」というフレーズの解釈は、いくつか存在します。
最も一般的な解釈は、「嫁に行った姐やの実家からの便り、ひいては姐や本人からの便りが途絶えてしまった」というものです。
嫁いだ後の姐やがどこでどうしているのか、全く分からなくなってしまったという状況です。
しかし、もう一歩踏み込んだ解釈も存在します。
それは、生き別れとなった実の母親に関する便りです。
露風の母親は離婚後、実家に戻っていました。
そして、その母親が、自分の代わりに息子の様子を知るために、近くに住んでいた姐やを子守りとして送り込んだのではないか、という説です。
この解釈によれば、姐やは露風にとって、母親の様子を伝えてくれる唯一の架け橋でした。
その姐やが嫁いでしまったことで、母親の消息を知る最後の手段さえ断たれてしまった。
それが「お里のたよりも絶えはてた」の真の意味だというのです。
この解釈に立つと、この歌は姐やへの思慕だけでなく、会うことのできない母への強い未練と絶望を歌っていることになり、より一層の悲壮感が漂います。
赤とんぼの歌詞に隠された怖い解釈

- 途絶えたお里の頼りが示す悲しい背景
- 4番の竿の先の意味が示す情景の変化
- 夕焼け小焼けの歌詞が怖いと言われる背景
- 総括:赤とんぼの歌詞が怖いと感じる理由
途絶えたお里の頼りが示す悲しい背景

前述の通り、「お里の頼りが絶えた」という一節は、単に手紙が来なくなったという事実以上の、深い断絶と孤独感を象徴しています。
当時の社会背景を考えると、その意味はさらに重くなります。
明治から大正にかけての時代、一度嫁いだ女性が実家と自由に連絡を取り合うことは、現代ほど簡単ではありませんでした。
また、「子守り奉公」という形で他家に仕える少女たちの立場は非常に弱く、奉公先や嫁ぎ先が変われば、以前の関係が完全に断ち切られてしまうことも少なくなかったのです。
さらに、離婚した母親と子供が会うことに対する社会的な障壁も現代よりずっと高い時代でした。
もし姐やが本当に母親との唯一の接点であったなら、彼女の嫁入りは露風にとって、母親との精神的な繋がりが完全に断絶したことを意味したでしょう。
このお里の便りが途絶えたという表現は、物理的な手紙だけでなく、心の拠り所であった人との絆が失われたことへの深い絶望感を表しているのです。
4番の竿の先の意味が示す情景の変化

4番
夕やけ、小やけの、赤とんぼ。とまつてゐるよ、竿の先。
歌詞の最後の4番は、それまでの過去の回想から一転して、現在の視点へと切り替わります。
「夕焼け小焼けの赤とんぼ とまっているよ竿の先」
1番の「負われて見た」赤とんぼは、温かい思い出の中の存在でした。
しかし、4番の赤とんぼは、成長した露風がたった一人で眺めている現在の情景です。
竿の先に静止している赤とんぼの姿は、まるで時が止まったかのようであり、独りでいる主人公の孤独な心象風景と重なります。
姐やの背中という温かい場所から見た赤とんぼと、今は一人で見つめる竿の先の赤とんぼ。
この対比によって、過ぎ去った時間と、もう戻らない日々への感傷が強く描き出されています。
幼い頃の鮮烈な思い出(1番)と、時を経て同じ風景を前に物思いにふける現在の自分(4番)とが、時空を超えて交錯する、非常に詩的な構成になっているのです。
夕焼け小焼けの歌詞が怖いと言われる背景

「赤とんぼ」の歌詞が「怖い」と感じられる理由は、都市伝説のような表面的なものではなく、歌詞の奥に潜む根源的な喪失感や孤独感にあります。
- 家庭の断絶
両親の離婚と母親との生き別れという、子供にとっては受け入れがたい現実が根底にあります。 - 愛する人との別離
母親代わりだった姐やとの突然の別れと、その後の消息不明という事実が、深い喪失感を与えます。 - 戻れない過去
楽しかった日々が「まぼろし」のようであったと語られることで、幸福な過去が決して戻らないものであることが強調されます。 - 孤独な現在
最後の4番で描かれる現在の情景が、主人公が今もなお一人でいることを示唆し、寂しさを際立たせています。
これらの要素が、美しい夕焼けの情景と相まって、一種の「物悲しさ」や「切なさ」を生み出します。
直接的に怖い言葉が使われているわけではありませんが、人間の心の奥底にある「失うことへの恐れ」や「孤独への恐怖」を静かに刺激するため、「怖い」という感情に結びつくことがあるのです。
総括:赤とんぼの歌詞が怖いと感じる理由

「赤とんぼ」の歌詞が怖いと感じられる理由を、以下にまとめます。
- 作詞は三木露風で、彼自身の幼少期の体験が基になっている
- 両親の離婚後、作者は祖父に育てられた
- 歌詞の「姐や」は実の姉ではなく、子守り奉公の少女
- 「負われて見た」は、姐やの背中に背負われて見た情景
- 「桑の実」は、姐やと過ごした楽しい日々の象徴
- 楽しい思い出が「まぼろしか」と表現され、儚さを強調
- 「十五で姐やは嫁に行き」は、母親代わりの存在との別れを意味する
- 「お里のたより」は、姐や、または生き別れた母からの便りと解釈される
- 便りが絶えたことは、大切な人との繋がりが完全に断絶したことを示す
- 4番は過去の回想ではなく、大人になった作者の現在の視点
- 竿の先の赤とんぼは、孤独な現在の心象風景と重なる
- 温かい過去の情景と、孤独な現在の情景が対比されている
- 歌詞の根底には、家庭の断絶や愛する人との別離というテーマがある
- 美しい情景描写と、その裏にある悲しい背景とのギャップが切なさを増幅させる
- 直接的な恐怖ではなく、喪失感や孤独感が「怖い」という感情を呼び起こす