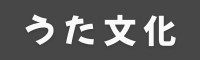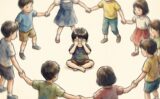幼い頃に何気なく歌っていた『ずいずいずっころばし』ですが、大人になってから改めて歌詞を振り返ると、意味がわからず不思議な不安を感じることがあります。
ネット上でも意味や「怖い」といった言葉と一緒に検索されることが多いこの歌には、実はお茶壺道中という江戸時代の歴史的な背景や、少しドキッとするような大人の都市伝説など、非常に多岐にわたる解釈が存在しているのです。
トッピンシャンという軽快な響きや「井戸のまわり」という場面設定に込められた謎について、現在語られているいくつかの説を順序立てて整理してみましょう。
結論としては、「怖い」とされる中心は「権威ある行列(お茶壺道中)に伴う緊張」を読み取る解釈と、「歌詞の断片から連想が広がった都市伝説」に大別されます。
ただし、いずれも確定的な“正解”として断言できるものではなく、複数の読みが併存しているのが実情です。
- お茶壺道中という権威が当時の庶民に与えた緊張感の実態
- トッピンシャンやドンドコショといった擬音に込められた意味
- 歌詞の裏に隠されたとされる性的な隠語や社会風刺の視点
- 井戸や茶碗にまつわる少し怖い伝承や他の童謡との共通点
ずいずいずっころばしの意味が怖いとされる歴史的背景

この楽曲が「怖い」と語られる最大の理由は、江戸時代に実在したある行列の恐ろしさを描いているとされるためです。
ここでは、最も有力な説として知られる「お茶壺道中」と歌詞の関係について、当時の社会状況を交えて解説します。
お茶壺道中の由来と恐ろしい権力の実像
『ずいずいずっころばし』の歌詞の由来として、最も広く知られているのが「お茶壺道中(宇治採茶使)」を描写したものだという説です。
これは江戸時代、京都の宇治で採れた新茶を将軍家に献上するために往来した行列のことを指します。
この行列が運ぶ茶壺は、単なる容器ではなく「将軍の代理」としての権威を持っていたといわれます。
そのため、行列の格式は徳川御三家の大名行列よりも上とされ、道中の警備や礼儀作法は極めて厳格でした。
もし行列に対して粗相があれば、手討ち(無礼討ち)にされる可能性もあったと伝えられており、沿道の庶民にとっては恐怖の対象であったと考えられます。
お茶壺道中(宇治採茶使)は、寛永9年(1632年)頃に制度化されたといわれています。行列が通る際、庶民は農作業を止め、土下座して通過を待つ必要がありました。
制度化の時期は徳川家の公式記録を踏まえて語られることがあり、地方自治体の公的資料でも寛永9年(1632年)頃の記述が確認できます。
都留市立図書館『御茶壺道中 その三』(広報つる 1994年6月12日号)
一方で、わらべうた自体は江戸時代の文献に見えず後世に定着した可能性も指摘されているため、行列の実態と歌詞の対応は「通説として結び付けられてきた解釈」として捉えるのが無難です。
京都産業大学 学術リポジトリ 若井勲夫「童謡・わらべ歌新釈(下)」
トッピンシャンの語源は戸締まりの音か

歌詞の中に登場する「トッピンシャン」という印象的なフレーズについては、いくつかの解釈が存在します。
お茶壺道中の文脈で語られる場合、これは大急ぎで家の戸締まりをする音を表しているという説が有力です。
「トッピン」は鍵をかける音や戸を閉める音、「シャン」は「しっかりと閉める(しゃんとする)」という動作の完了を意味していると読むことができます。
行列が近づいてくる気配を感じ、慌てて雨戸や障子を閉めて、外部との関わりを遮断しようとする庶民の緊迫した様子が、このリズムの良い言葉に込められているのかもしれません。
ただし、わらべうたは地域差・伝承差で音や言い回しが変わりやすく、擬音の解釈は「語感からの当てはめ」になりやすい点に留意が必要です。意味を一つに固定するより、「戸を閉める切迫感」を象徴的に表した読みとして位置付けると理解しやすくなります。
茶壺に追われて閉じこもる庶民の恐怖
「茶壺に追われて」という歌詞は、まさに行列の接近によって、人々が路上から家の中へと追いやられる状況を表しているといえます。
行列の先触れが「下に、下に」と声を上げたり、役人が先行してきたりすることで、村全体が物音ひとつ立てられない静寂に包まれる様子が想像できます。
当時の記録などを参照すると、行列が通過する際は煮炊きの煙を上げることすら「お茶の香りを損なう」として忌避されたという話もあります。
親たちは子供が外で騒いで処罰されることを恐れ、「静かにしていなさい」と家の中に閉じ込めたことでしょう。
「おっとさんが呼んでもおっかさんが呼んでも行きっこなしよ」という歌詞は、そうした非常事態における「絶対に出てはいけない」というルールの厳しさを物語っていると考えられます。
俵のねずみや米食ってが示す飢饉と貧困

家の中に息を潜めて閉じこもっている間、唯一自由に動ける存在として描かれているのが「俵のねずみ」です。
人間は権力を恐れて身動きが取れない一方で、ネズミだけが俵の米を食い荒らしているという対比は、ある種の皮肉や無力感を含んでいるように感じられます。
また、この描写をもう少し暗い側面から読み解く説もあります。
大切な食糧である米がネズミに食われていても、物音を立てて追い払うことすらできない状況や、あるいはネズミしか生き残っていないような荒廃したイメージから、飢饉や貧困のメタファーではないかと推測する見方もあります。
静まり返った家の中で、ネズミの鳴き声や齧る音だけが響く光景は、独特の不気味さを漂わせています。
「チュウ」という言葉はネズミの鳴き声とするのが一般的ですが、別の解釈として「接吻の音」などを連想させるという説(後述の性的隠語説など)も存在します。
抜けたらドンドコショで感じる安堵の正体
長い緊張状態の果てに訪れるのが、「抜けたらドンドコショ」という結末です。
「抜けたら」とは、お茶壺道中の行列が村を通り過ぎ、村境を越えて去っていったことを指すと考えられます。
そして「ドンドコショ」は、張り詰めていた空気が緩み、「やれやれ」と安堵するため息をつく様子や、停止していた日常生活や労働を再開する際の掛け声を表現しているといわれます。
このフレーズからは、権力の圧力から解放された民衆の喜びや、たくましさが感じ取れるかもしれません。
ずいずいずっころばしの意味と怖い都市伝説の真相

歴史的な背景とは別に、この歌には大人向けの際どい解釈や、怪談めいた都市伝説も語り継がれています。
ここでは、民俗学的な視点や雑学として語られることの多い「もう一つの意味」について解説します。
性的隠語とされる夜鷹やごまみそずいの謎
ネット上の検索結果などでよく見かけるのが、歌詞に性的な隠語(メタファー)が含まれているという説です。
この解釈では、江戸時代の最下層の私娼である「夜鷹」や、男女の情事を描いた歌ではないかと推測されることがあります。
例えば、「ずっころばし」は「蹴っころばし」が訛ったもので夜鷹の蔑称であるとする説や、「ごまみそずい」は「こまいしょつい(ご面倒でしょうが)」という客引きの言葉が変化したものであるという説などが存在します。
これらはあくまで言葉遊びの範疇を出ない推測も多いですが、わらべうたが持つ「意味不明さ」が、こうした大人の想像力を掻き立てる要因になっているといえそうです。
この種の読みは「隠語の可能性」を手掛かりに歌詞全体を組み立て直すため、当時の用例や語の転訛(変化)の根拠がどこまで示せるかで説の強度が変わります。
裏付けが示されない断定は避け、あくまで「そう読む見方がある」という距離感で受け取るのが安全です。
西沢爽説が唱える大人の風刺と怖い解釈
前述の性的な解釈を体系的に論じた人物として、昭和期の歌謡史研究家である西沢爽氏の名前が挙がることがあります。
西沢氏の説などによれば、一見無邪気な歌詞の端々に、当時の庶民のエネルギッシュな性風俗や、社会に対する風刺が込められていると読み解くことができます。
この視点に立つと、「茶壺」や「俵」といった言葉もまた、女性の身体や行為を暗示する隠語として再構成されることがあります。
「怖い」というよりは「猥雑」に近いニュアンスですが、子供が意味もわからず歌っているその裏に、大人たちの生々しい世界が隠されているという構図自体が、現代の感覚からするとある種の「怖さ」を感じさせるのかもしれません。
これらの性的解釈は一つの説に過ぎません。地域や時代によって歌詞のバリエーションも多く、必ずしも全ての元歌がこうした意味を含んでいたとは限らない点に注意が必要です。
井戸のまわりでお茶碗欠いた子供の処刑説

楽曲の最後、「井戸のまわりでお茶碗かいたのだあれ」というフレーズには、悲しい伝承が付随して語られることがあります。
「かいた」は「欠いた(割った)」を意味します。
ある屋敷で奉公していた子供が、主人の大切な茶碗(一説にはお茶壺道中の献上品)を誤って割ってしまい、その罰として井戸に投げ込まれたり、手討ちにされたりしたという話です。
この説に基づくと、歌全体がその子供の鎮魂歌である、あるいは「ルールを破るとこうなる」という戒めの歌であるという解釈が成り立ちます。
「だあれ」という問いかけが、井戸の底からの呼び声のように聞こえるという怪談的な捉え方も、この歌の怖さを増幅させています。
ただし、この種のエピソードは「歌詞の雰囲気」から後に物語化された可能性もあり、特定の事件記録に直接結び付く形で確定するのは容易ではありません。史料で裏付けが示されない限り、伝承・都市伝説として扱うのが中立的です。
かごめかごめや通りゃんせも怖い童謡か

『ずいずいずっころばし』に限らず、日本の童謡には「実は怖い意味がある」と噂されるものが数多く存在します。
『かごめかごめ』の「後ろの正面」や、『通りゃんせ』の「帰りは怖い」といったフレーズは、神隠しや人柱、あるいは流産といった重いテーマと結びつけて語られることが少なくありません。
個別の歌については、説の種類と根拠の出どころを分けておくと、誤解(断定・拡散)を避けやすくなります。
なぜ童謡にこれほど怖い説がつきまとうのでしょうか。
一つには、昔の日本に存在した貧困や厳しい身分制度などの「負の歴史」が、現代人にとってはリアリティのない物語となり、それが都市伝説という形で消費されている側面があると考えられます。
また、明るいメロディーと意味深な歌詞のギャップが、心理的な不気味さを生んでいるともいえるでしょう。
よくある質問:ずいずいずっころばしの意味と由来
- Qお茶壺道中説は「事実」として確定しているのですか?
- A
お茶壺道中そのものは史料で語られますが、歌詞との対応は「通説として結び付けて読む解釈」とされます。確定的に断言できる材料が十分かは別問題として扱うのが中立的です。
- Q「トッピンシャン」は戸締まりの音で決まりですか?
- A
戸締まりの擬音と読む説は有力ですが、わらべうたは伝承で音が変わりやすく、別の読みも成り立ちます。断定よりも「切迫感を表す言葉」として捉えると整理しやすいです。
- Q性的隠語説は根拠がありますか?
- A
近世語や隠語の用例から説明を試みる説がありますが、地域差や推測が入りやすい領域です。一般に、裏付けの提示がない断定は避け、説の一つとして距離を取って読むのが安全です。
- Q歌詞は全国で同じですか?
- A
わらべうたは地域や時代で歌詞の揺れが起きやすく、同じ題名でも言い回しが異なることがあります。一般的な目安として代表的な歌詞が流通していると考え、正確には地域の採録資料で確認するのが確実です。
ずいずいずっころばしの意味は本当に怖いか総括
ここまで見てきたように、『ずいずいずっころばし』の意味については、お茶壺道中における権力への恐怖を描いたもの、性的な風刺を含んだもの、あるいは奉公人の悲劇を伝承したものなど、複数の層が重なり合っています。
これらが「唯一の正解」というわけではなく、長い年月の中で様々な意味が付与され、語り継がれてきたというのが実情でしょう。
しかし、どの説にも共通しているのは、かつての日本の庶民が感じていた緊張感や、理不尽な状況下での感情が込められているという点です。
「怖い」と感じるその感覚の正体は、歌詞の向こう側に透けて見える、歴史の中で生きた人々の切実な息遣いなのかもしれません。