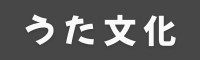イギリス国歌の歌詞や和訳を知りたいけれど、なんだか怖い噂もあって気になっているという方も多いのではないでしょうか。
サッカーやラグビーの国際大会を見ていると、イングランド代表とスコットランド代表で歌っている曲が違うことに気づき、イギリスの国歌事情について疑問を持つこともありますね。
実はこの曲、アメリカやリヒテンシュタインでもメロディが同じだったり、最近歌詞が変更されたりと、非常に奥深い歴史を持っています。
この記事では、そんなイギリス国歌に関するさまざまな謎や背景を紐解いていきます。
- God Save the Kingの歌詞の意味と日本語訳
- 怖い歌詞と言われる都市伝説の真相と歴史
- スポーツ大会で国歌が異なる複雑な事情
- 同じメロディを持つ他国の国歌との関係
イギリス国歌の歌詞の意味と怖い都市伝説
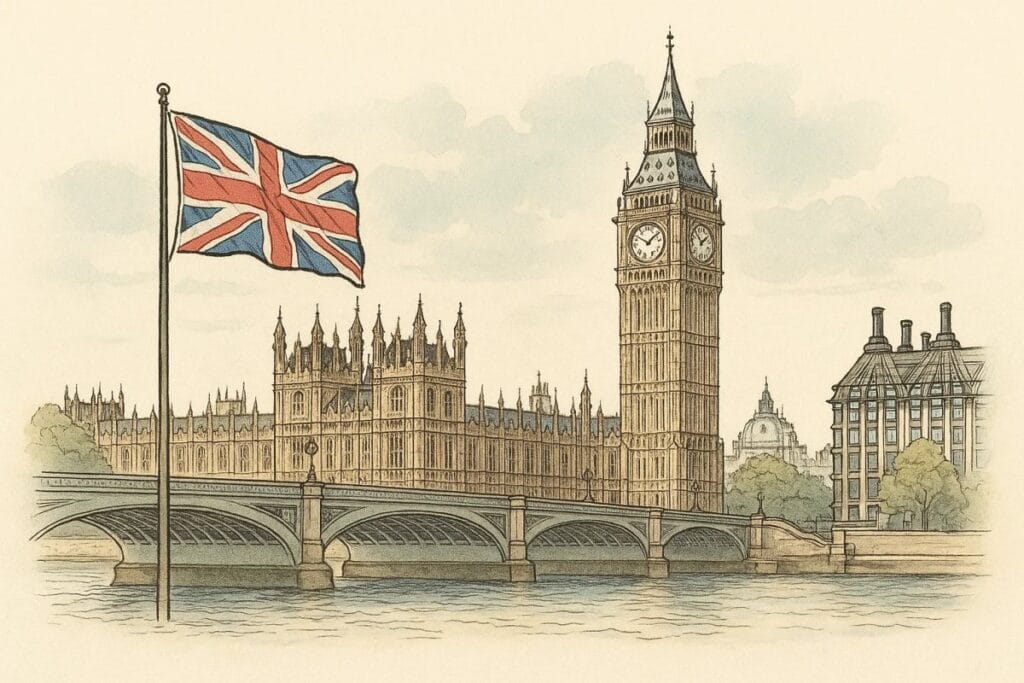
イギリス国歌として知られる「God Save the King」は、法律で定められたものではなく、長年の慣習によって国民に定着した「事実上の国歌」です。
ここでは、その歌詞に込められた意味や、ネット上でささやかれる「怖い歌詞」の真相、そして意外な他国との共通点について掘り下げていきます。
God Save the Kingの歌詞と和訳
God Save the King(神よ国王を守り給え)の歌詞は、非常にシンプルでありながら、君主への深い忠誠と国家の安寧を祈る内容となっています。
基本的には第1番のみが歌われることが多いですが、式典などでは第2番まで歌われることもあります。
私が理解している範囲での意訳を紹介します。
第1番
God save our gracious King!
(神よ、我らが慈悲深き国王を守り給え!)
Long live our noble King!
(我らが高貴なる国王よ、万歳!)
God save the King!
(神よ、国王を守り給え!)
Send him victorious,
(彼に勝利をもたらし、)
Happy and glorious,
(幸福にして栄光あれ、)
Long to reign over us,
(我らの上に長く君臨せんことを、)
God save the King.
(神よ、国王を守り給え。)
このように、歌詞全体が君主の身体的な安全と、その治世の繁栄を神に願う「祈り」の構造になっています。
「Save」という言葉は単に「救う」というより、王という存在を「保全する」「守り抜く」というニュアンスが強いと考えられますね。
女王から国王への歌詞変更のポイント
2022年9月、長きにわたって在位したエリザベス2世女王が崩御し、チャールズ3世が新国王として即位しました。
これに伴い、国歌の歌詞も約70年ぶりに変更されました。
具体的には、これまで「Queen(女王)」と歌われていた部分がすべて「King(国王)」に置き換わり、代名詞も女性形の「her/she」から男性形の「him/he」へと変わりました。
- 変更前
God Save the Queen - 変更後
God Save the King
たった数語の違いですが、長年「Queen」と歌い慣れてきたイギリス国民にとっては、身体に染み付いた習慣を変える大きな出来事だったと言えます。
スポーツの試合などで、感極まったファンや選手がつい「Queen」と歌ってしまい、慌てて言い直すような場面も見受けられました。
これは単なる言葉の変更以上に、時代の節目を象徴する現象だと感じます。
イギリス国歌は怖い?幻の歌詞の真相
「イギリスの国歌」を調べると、「怖い」というキーワードが出てくることがあります。
これは主に、かつて存在したとされる「スコットランド人を粉砕せよ」という過激な歌詞に由来しています。
この歌詞は「Marshal Wade Verse」と呼ばれ、1745年の反乱鎮圧の際に一時的に歌われたものだと言われています。
May he sedition hush,
(彼が反乱を鎮め、)
And like a torrent rush,
(奔流のごとく押し寄せ、)
Rebellious Scots to crush,
(反抗的なスコットランド人を粉砕せんことを、)
確かに、特定の民族を「粉砕する」と歌うのは現代の感覚では非常に恐ろしいことですよね。
しかし、重要なのはこの歌詞が公式な国歌として定着した事実はなく、現在は全く歌われていないという点です。
あくまで歴史的な一場面で生まれた「幻の歌詞」であり、現在のイギリス国歌にこのような攻撃的な意図は含まれていません。
ただ、スコットランド独立運動などの政治的な文脈で、イングランドによる抑圧の象徴としてこの歌詞が引き合いに出されることはあるようです。
アメリカやリヒテンシュタインと同じ曲
驚かれるかもしれませんが、イギリス国歌のメロディは世界中で使い回されてきた歴史があります。
例えば、ヨーロッパの小国リヒテンシュタインの国歌「Oben am jungen Rhein(若きライン川のほとり)」は、イギリス国歌と全く同じメロディです。
そのため、サッカーの予選などでイングランドとリヒテンシュタインが対戦すると、試合前に同じ曲が2回連続で流れるという珍しい光景が見られます。
また、アメリカ合衆国でもこのメロディは「My Country, ‘Tis of Thee(マイ・カントリー・ティズ・オブ・ジー)」という愛国歌として親しまれています。
アメリカ国歌「星条旗」が正式に採用される前は、事実上の国歌のような扱いを受けていた時期もありました。
王政を否定して独立したアメリカが、王を讃える歌と同じメロディを使っているというのは、歴史の皮肉を感じさせますね。
1745年の危機から生まれた歴史と起源
この歌が「国歌」としての地位を確立したのは、1745年のジャコバイトの反乱という歴史的事件がきっかけでした。
当時、カトリック系のスチュアート家の復権を目指す勢力がスコットランドから攻め上がり、ロンドンの政府は大きな危機感を抱いていました。
そんな中、ロンドンの劇場で国王への忠誠を示すためにこの歌が演奏され、観客が大合唱したことで爆発的に広まりました。
つまり、誰か一人の作曲家が「国歌を作ろう」として作ったのではなく、国家の危機に際して民衆の中から自然発生的に沸き起こった「祈り」や「応援歌」が、そのまま定着したというわけです。
作曲者は「不詳」とされていますが、17世紀の作曲家ジョン・ブルなどの作品に類似した旋律が見られることから、当時の音楽的な共有財産の中から生まれたメロディだと考えられます。
スポーツ大会でのイギリス国歌の複雑な事情

オリンピックでは「英国代表」として出場しますが、サッカーやラグビーのワールドカップでは、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドがそれぞれ個別のチームとして出場します。
そのため、どの国歌を歌うかという問題は非常に複雑で、それぞれの地域のアイデンティティが色濃く反映されています。
サッカーイングランド代表の国歌問題
サッカーのイングランド代表は、伝統的にイギリス全体の国歌である「God Save the King」を使用しています。
しかし、これに対しては国内でも議論があります。
「スコットランドやウェールズは独自の歌を持っているのに、なぜイングランドだけがイギリス全体の歌を使うのか?」「これではイングランド独自のアイデンティティが見えない」といった意見です。
そのため、クリケットなどの一部の競技では、ウィリアム・ブレイクの詩によるJerusalem(エルサレム)という曲がイングランドの国歌として使用されることがあります。
この曲は「産業革命で汚されたイングランドの地に、理想郷(エルサレム)を築こう」という壮大な内容で、多くのイングランド人から愛されています。
「God Save the King」よりもこちらを正式なイングランド国歌にすべきだという声も根強く存在します。
スコットランド国歌「花のスコットランド」
スコットランド代表が使用するのは、フォークソンググループ「ザ・コリーズ」が作ったFlower of Scotland(スコットランドの花)です。
この歌は、1314年のバノックバーンの戦いで、スコットランド軍がイングランド軍を破った歴史的勝利をテーマにしています。
歌詞の中には「誇り高きエドワード王の軍を追い返した」といった内容が含まれており、イングランドに対する強烈な対抗心が込められています。
「God Save the King」が「王への忠誠」を歌うのに対し、この曲は「独立心と自由」を鼓舞する歌です。
そのため、マレーフィールド・スタジアムなどで大合唱される際の熱気はすさまじく、単なるスポーツの応援を超えた民族の魂の叫びを感じさせます。
ウェールズ国歌とラグビーの熱狂
歌の国として知られるウェールズでは、「Hen Wlad Fy Nhadau(我が父祖の土地)」という独自の国歌が歌われます。
ラグビーの試合前、カーディフのミレニアム・スタジアムでこの歌が歌われる光景は、世界中のラグビーファンにとって特別な瞬間です。
選手も観客も涙を流しながら歌う姿は、ウェールズ語という独自の言語と文化を守り抜いてきた彼らの誇りを象徴しています。
ウェールズの場合、反イングランドというよりも、自分たちの美しい国土と言語への純粋な愛情が表現されている点が特徴的だと私は感じます。
北アイルランド国歌とダニーボーイ
北アイルランドの事情はさらに複雑です。
プロテスタント系住民(英国帰属派)とカトリック系住民(アイルランド統一派)の対立の歴史があるため、国歌の選択は政治的な意味を持ってしまいます。
サッカーの北アイルランド代表は「God Save the King」を使用しますが、これに対してブーイングが起きることもあります。
一方、イギリス連邦の大会(コモンウェルスゲームズ)などでは、政治的な中立性を保つために、Danny Boy(ダニー・ボーイ)のメロディとして知られる「ロンドンデリーの歌」が使われることがあります。
また、ラグビーのアイルランド代表は、北アイルランドとアイルランド共和国の合同チームであるため、試合では「Ireland’s Call(アイルランド・コール)」という、両者の融和を願って作られた新しいアンセムが歌われます。
これにより、政治的な対立を超えてチームが一つになることを目指しているのです。
オリンピックイギリス代表の国歌事情
オリンピックにおいては、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの選手が「Team GB(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国代表)」として一つのチームを結成します。
そのため、表彰式で流れるのは共通の「God Save the King」です。
しかし、スコットランドやウェールズ出身の選手の中には、この歌を歌うことに複雑な感情を抱く人もいます。
自身のアイデンティティは「イギリス人」である前に「スコットランド人」であると考える選手も少なくないからです。
過去には、北アイルランド出身のプロゴルファーが、どの国の代表として出場するか、どの国歌の下でプレーするかという問題に悩み、苦渋の決断を迫られたケースもありました。
スポーツの祭典であっても、国歌が突きつける「国家への帰属意識」というテーマは、選手たちにとって重い問いかけとなっているようです。
まとめ:歴史に見るイギリス国歌の魅力
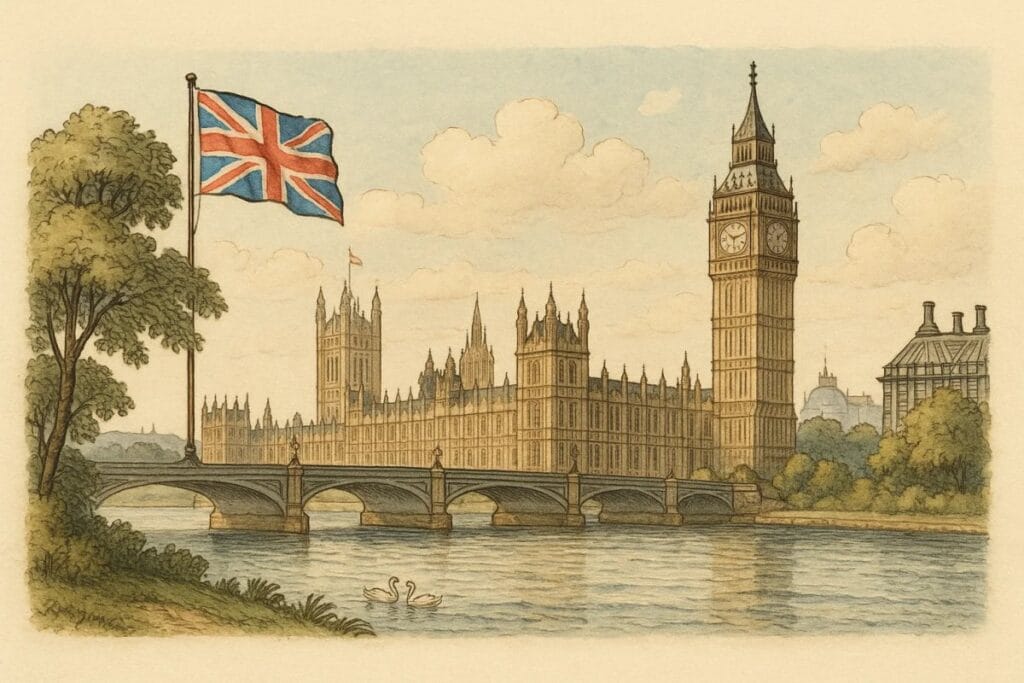
イギリス国歌「God Save the King」は、単なる君主を称える歌という枠を超え、連合王国の複雑な成り立ちや、構成国それぞれの誇りと葛藤を映し出す鏡のような存在だと言えます。
1745年の危機から生まれ、世界中にメロディが広まり、現代ではスポーツを通じて新たなナショナリズムの表現と向き合っています。
次にテレビでこの国歌、あるいはスコットランドやウェールズのアンセムを耳にしたときは、その背景にある長い歴史や人々の想いに耳を傾けてみてはいかがでしょうか。
そうすることで、試合の景色がまた違って見えてくるはずです。