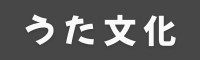サッカーの国際試合やF1グランプリを見ていると、ひときわ陽気で、かつ情熱的に歌われる国歌が耳に残ることがあります。
それが「イタリア国歌」です。
特にF1ファンの方であれば、真紅のフェラーリが勝利した表彰台で流れるあのメロディに、特別な感情を抱くことも多いのではないでしょうか。
しかし、その明るい曲調とは裏腹に、歌詞の意味を紐解くと「死」や「血」といった言葉が並ぶ、非常に激しい内容であることはあまり知られていません。
また、なぜ歌詞の中に他国であるポーランドが登場するのか、といった歴史的な謎も隠されています。
今回は、この楽曲が持つ多層的な背景と、現代のスポーツシーンにおける熱狂の理由を、歴史的文脈から論理的に分析していきます。
- 正式名称「マメーリの賛歌」の由来と歌詞に込められた歴史的暗号
- 明るい曲調の中に「死」や「血」という言葉が含まれる背景
- 歌詞の中にポーランドという他国の名前が登場する地政学的な理由
- F1の表彰台でフェラーリ勝利時にファンが「Sì!」と叫ぶ意味
イタリア国歌の歌詞や意味を徹底解説

イタリア国歌は、単なる愛国歌という枠を超え、19世紀のイタリア統一運動(リソルジメント)の精神がそのまま凍結保存された歴史的史料であると言えます。
ここでは、その正式名称や歌詞に隠された「暗号」のような歴史的引用について、具体的に分析していきます。
マメーリの賛歌という正式名称
一般的に「イタリア国歌」として検索されるこの楽曲ですが、イタリア本国ではマメーリの賛歌(Inno di Mameli)や、その歌い出しである『イタリアの兄弟』(Fratelli d’Italia)と呼ばれることが一般的です。
しかし、法的な正式名称は『イタリア人たちの歌』(Il Canto degli Italiani)となります。
この曲が作られたのは1847年です。
当時のイタリアはまだ一つの国家として統一されておらず、オーストリア帝国や教皇領などに分断されていました。
そのような状況下で、ジェノヴァの若き学生ゴッフレード・マメーリが作詞し、ミケーレ・ノヴァーロが作曲したこの歌は、既存の国家を称えるものではなく、これから国家を作るために立ち上がる人々を鼓舞するための「行進曲」として誕生したのです。
日本語訳やカタカナで見る歌詞
歌詞の冒頭部分を紐解くと、当時のイタリア人が置かれていた状況と、古代ローマへの憧れが鮮明に読み取れます。
Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta,
(フラテッリ ディターリア、リターリア セ デスタ)
イタリアの兄弟よ、イタリアは目覚めたDell’elmo di Scipio s’è cinta la testa.
(デッレルモ ディ シーピオ セ チンタ ラ テスタ)
スキピオの兜をその頭に被った
ここで登場する「スキピオ」とは、古代ローマ時代の英雄スキピオ・アフリカヌスのことです。
かつてハンニバル率いるカルタゴ軍を破った英雄の兜を被るということは、現代のイタリア人が古代ローマの栄光と不敗の精神を取り戻したことを宣言していると解釈できます。
さらに続く歌詞では、「勝利の女神(ウィクトーリア)はどこだ? 彼女に髪を差し出させよ」と歌われます。
古代ローマでは奴隷の髪を刈る習慣があり、「勝利の女神は神によってローマ(イタリア)の奴隷として創られたのだから、我々の勝利は必然である」という、非常に強気なレトリックが用いられているのです。
歌詞の内容が怖いと言われる理由
イタリア国歌が「怖い」と評されることがあるのは、主にコーラス部分の激しい表現に起因します。
Stringiamci a coorte, siam pronti alla morte.
(ストリンジャンチ ア コオルテ、シアム プロンティ アッラ モルテ)
歩兵隊(コオルテ)を組め、我らは死ぬ覚悟ができているSiam pronti alla morte, l’Italia chiamò.
(シアム プロンティ アッラ モルテ、リターリア キアモ)
我らは死ぬ覚悟ができている、イタリアが呼んでいる
「死ぬ覚悟ができている(Siam pronti alla morte)」というフレーズが2度も繰り返されます。
これは比喩ではなく、当時の革命家たちにとって現実的な選択でした。
彼らにとって国歌は、平和な祭典で歌うものではなく、圧倒的な軍事力を持つオーストリア帝国軍に向かって突撃する際に、恐怖を振り払うために歌うアジテーション(扇動)の道具だったと言えます。
ポーランドが歌詞に登場する意味
この国歌の最大の特徴の一つであり、多くの人が疑問に思う点が、歌詞の第5節に「ポーランドの血」というフレーズが登場することです。
Il sangue d’Italia, il sangue Polacco,
イタリアの血を、ポーランドの血をBevé, col cosacco, ma il cor le bruciò.
(オーストリアの鷲は)コサック(ロシア)と共に飲んだが、その血は鷲の心臓を焼いた
ここで言及されているのは、18世紀後半に行われた「ポーランド分割」です。
当時、ポーランドはオーストリア、ロシア、プロイセンによって国土を奪われ、国家として消滅していました。
イタリアもまた、オーストリアの支配下にあり、同じ「分断された痛み」を持つ同志としてポーランドへの連帯を示しているのです。
歌詞は「オーストリアの鷲(ハプスブルク家)が、イタリアやポーランドの血をすすったが、その血は毒となって鷲を滅ぼすだろう」という、強烈な呪詛と抵抗のメッセージを含んでいます。
自国の国歌に他国の悲劇を引用し、共闘を呼びかける例は世界的に見ても極めて稀であり、当時の地政学的な連帯感を物語る貴重な資料と言えるでしょう。
若き作詞者マメーリの生涯
この情熱的な歌詞を書いたゴッフレード・マメーリは、どのような人物だったのでしょうか。
彼がこの詩を書いたのは、なんと弱冠20歳の時でした。
マメーリは単なる詩人ではなく、剣をとって戦う革命家でもありました。
彼はジュゼッペ・マッツィーニやジュゼッペ・ガリバルディといった英雄たちと共に戦場を駆け抜けましたが、1849年、ローマ共和国の防衛戦において左脚を負傷し、その傷がもとで21歳という若さで命を落としました。
彼が歌詞に込めた「死ぬ覚悟はできている」という言葉は、決して空虚なスローガンではなく、彼自身の生き様そのものであったと言えます。
この「若さ」と「犠牲」の物語が、現代においてもイタリア人の心に深く響く理由の一つであると考えられます。
F1や歴史から見るイタリア国歌の魅力

歴史的な背景を理解した上で、現代のシーン、特にF1グランプリにおけるイタリア国歌の扱いを見ると、その特異性がより際立ちます。
ここでは、法的な位置づけの変化や、スポーツにおける「儀式」としての側面を解説します。
2017年に制定された歴史的背景
驚くべきことに、この『マメーリの賛歌』が法律で正式にイタリアの国歌として制定されたのは、2017年のことです。
1861年のイタリア統一から第二次世界大戦後の1946年までは、王家を称える『王室行進曲』が国歌でした。
共和制移行後の1946年に『マメーリの賛歌』が暫定的に採用されましたが、正式な法令がないまま、71年間も「事実上の国歌」として歌われ続けてきたのです。
2017年12月、ようやく法律第181号によって正式な国歌としての地位を獲得しました。
長らく「仮の姿」であったこの曲が、法的な裏付けを得たのはごく最近の出来事であり、これはイタリアという国家の運営における複雑さを象徴しているようにも見えます。
F1の表彰台で流れる特別な国歌
モータースポーツの最高峰F1において、国歌は非常に重要な意味を持ちます。
表彰式では、優勝したドライバーの国歌と、優勝したコンストラクター(チーム)の国歌の2曲が演奏される決まりがあります。
スクーデリア・フェラーリはイタリア国籍のチームです。
そのため、フェラーリのドライバーが優勝すると、ドライバーの国歌に続いてイタリア国歌が流れます。
もしイタリア人ドライバーがフェラーリで優勝すれば、イタリア国歌が2回流れることになりますが、近年は多国籍なドライバーが活躍しているため、異なる2つの国歌が続くことが一般的です。
モンツァ・サーキットで開催されるイタリアGPでは、レース前の国歌斉唱が一大イベントとなります。
上空をイタリア空軍の曲技飛行隊「フレッチェ・トリコローリ」が飛び、緑・白・赤のトリコローレ(三色旗)のスモークを描く光景は、F1カレンダーの中でも屈指の美しさと情熱を誇ります。
フェラーリ勝利時に歌うファンの熱量
フェラーリが勝利した際の表彰台の下は、まさにカオスと歓喜の渦となります。
「ティフォシ」と呼ばれる熱狂的なフェラーリファンたちは、巨大なフェラーリの旗を広げ、国歌を大合唱します。
この時、彼らが歌っているのは単なる歌ではなく、自分たちのアイデンティティそのものです。
歴史的に分断されていたイタリアにおいて、フェラーリとサッカー代表(アズーリ)は、国民を一つにする数少ない「宗教」のような存在と言えます。
その中心にあるのがこの国歌であり、勝利の瞬間に全員で声を合わせる行為は、彼らにとって至上の喜びなのです。
曲の最後に叫ぶ合いの手の正体
イタリア国歌の演奏が終わる直前、音楽がジャン!と終わるタイミングに合わせて、全員で「Sì!(スィ!)」と叫ぶのを聞いたことがあるでしょうか。
実はこの「Sì!」という叫びは、マメーリの書いた元の歌詞には存在しません。
作曲者のノヴァーロが、曲の力強さを増すために追加した演出だと言われています。
歌詞の「死ぬ覚悟はできている、イタリアが呼んでいる」という問いかけに対し、「そうだ!(その通りだ!)」と力強く答える兵士たちの声を表現していると解釈されます。
F1の表彰台でも、このタイミングでティフォシたちが一斉に拳を突き上げて叫ぶ姿が見られます。
これは単なる合いの手ではなく、歌詞の物語を完結させるための重要な儀式の一部なのです。
歴史を知りイタリア国歌を楽しむ

「イタリア国歌」は、陽気なメロディの中に、独立戦争の血なまぐさい記憶と、若者たちの命をかけた決意が込められた楽曲です。
スキピオの兜やポーランドへの連帯といった歴史的背景を知ることで、F1やサッカーの試合で流れるこの歌が、まったく違った深みを持って聞こえてくるはずです。
もし次にフェラーリが勝利し、この国歌が流れる瞬間に出会ったら、ぜひ最後の「Sì!」の叫びまで注目してみてください。
そこには、1847年から続くイタリア人たちの魂の叫びが込められているのです。
本記事の情報は歴史的資料や一般的な解釈に基づいています。正確な歴史的事実や最新の法的状況については、公的な専門機関の資料もあわせてご確認ください。