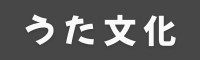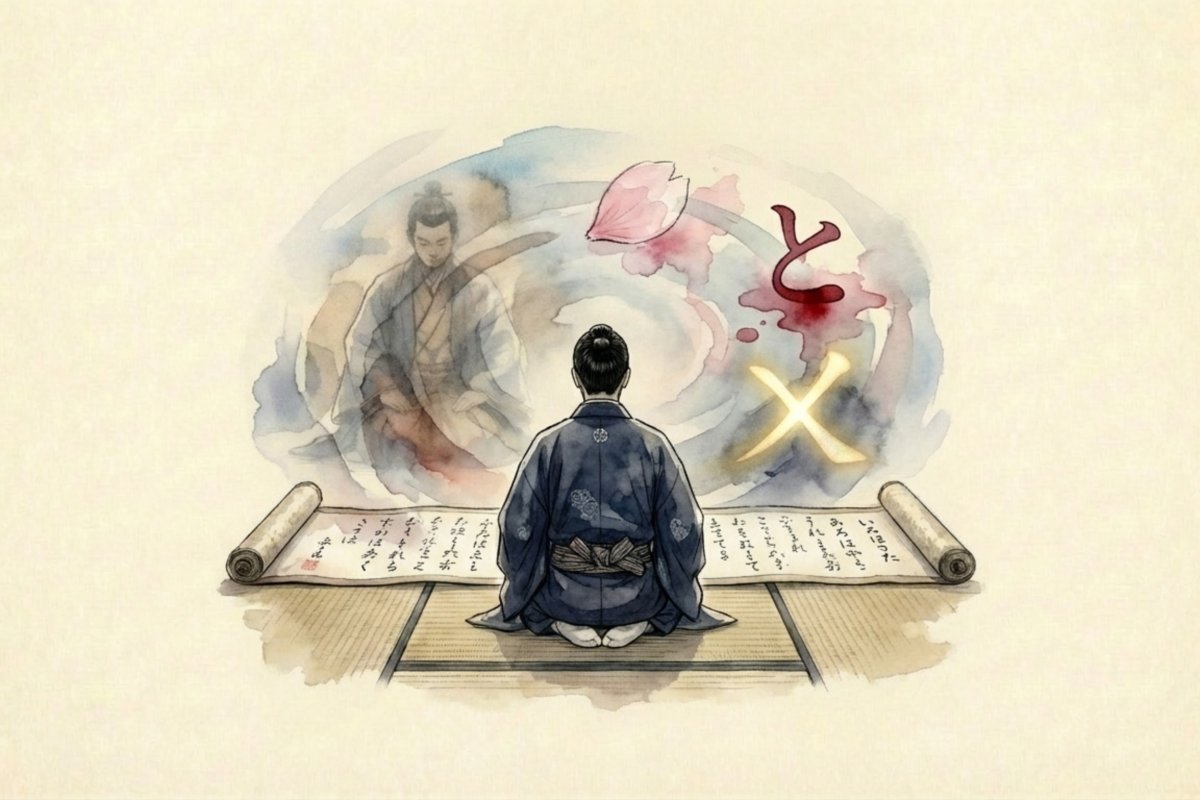子どもの頃から親しんできた「いろはにほへと」の歌に、実は恐ろしい意味や呪いが隠されているという話を聞いたことはないでしょうか。
学校では美しい日本語の練習として習いますが、ネット上では「咎なくて死す」という暗号や逆再生にまつわる不気味な噂、さらにはキリスト教との関わりまで、さまざまな都市伝説が語られています。
なぜこの短い歌にこれほど多くのミステリーが囁かれるのか、その背景にある歴史や心理的な理由を詳しく知りたいという方も多いはずです。
- 縦読みすることで現れるとされる「死の暗号」の具体的な内容
- 江戸時代から続く呪いの噂と歴史的な背景
- 逆再生やキリスト教説など現代に広まる都市伝説の検証
- いろは歌が本来持っている仏教的な意味と成立の経緯
結論を先にまとめると、いろは歌に「呪い」が仕込まれていたと断定できる一次史料は確認されていません。
一方で、特定の区切り方で「とがなくてしす」と読めること自体は古くから知られ、解釈の違いがさまざまな物語を生んできた、という整理が最も現実的です。
いろは歌の意味が怖い理由は暗号にある?

いろは歌が単なる手習いの歌ではなく「怖い」と言われる最大の理由は、特定の読み方をすると浮かび上がるとされる不穏なメッセージの存在にあります。
ここでは、古くから指摘されてきた暗号の仕組みと、そこに投影された歴史上の悲劇について解説します。
縦読みすると現れる咎なくて死すの暗号
いろは歌に隠された暗号として最も有名なのが、「咎(とが)なくて死す」という言葉です。
これは、いろは47文字を7文字ごとに区切って改行し、一番最後の文字(7文字目)を縦に読んでいくと現れる文字列とされています。
具体的には、以下のような配列になります。
| 行数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1行目 | い | ろ | は | に | ほ | へ | と |
| 2行目 | ち | り | ぬ | る | を | わ | か |
| 3行目 | よ | た | れ | そ | つ | ね | な |
| 4行目 | ら | む | う | ゐ | の | お | く |
| 5行目 | や | ま | け | ふ | こ | え | て |
| 6行目 | あ | さ | き | ゆ | め | み | し |
| 7行目 | ゑ | ひ | も | せ | す |
※7行目の「す」の位置については、47文字で終わるため本来は5文字目に来ますが、暗号説では末尾の列として扱われることが多いです。
この「と・か・な・く・て・し・す」をつなげると、「罪もないのに処刑される」という意味に解釈できることから、無実の罪で葬られた人物の怨念が込められているのではないかと言われています。
ただし、「とがなくてしす」は古い辞書では「罪や過失と無縁のまま生涯を終える(=咎なく生を終える)」という方向で説明されることもあります。
どちらの読みを採るかで、同じ並びが「怨念」にも「無常の教え」にも結びつく点が、この噂の広まりやすさを支えてきました。
「咎なくて死す」の意味
「咎(罪や過失)」がないにもかかわらず「死す(殺される)」という、冤罪に対する強い憤りや無念を表す言葉として解釈されています。
7文字区切りの法則と折句という技法
この「7文字ごとに区切って読む」という解読方法は、現代の誰かが勝手に作ったこじつけのように思えるかもしれませんが、実は歴史的な裏付けがあるとも言えます。
平安時代の和歌には、「折句(おりく)」や「沓冠(くつかぶり)」といった言葉遊びの技法が存在しました。
これは、歌の各句の頭文字や末尾の文字をつなげると、別の意味や名前が隠されているというものです。
在原業平が「かきつばた」の5文字を句頭に詠み込んだ歌などが有名です。
また、1079年頃に成立した『金光明最勝王経音義』という文献では、実際にいろは歌が7文字ごとのブロックで区切って記載されていることが確認できます。
当時は検索用の索引としてこの形が使われていたようですが、この形式自体が古くから存在していたことは事実と言えます。
一方で、古い文献に「7文字区切りの書き方」があることと、「縦読みによるメッセージを作者が意図した」ことは別問題です。
索引・配列の都合で区切られた可能性もあり、意図の有無は史料だけで確定しにくい点は押さえておきたいところです。
そのため、作者がこの「7文字区切り」のフォーマットを利用して、意図的にメッセージを埋め込んだ可能性を指摘する声もあります。
また、いろは歌が「文字を覚える歌」として実際に使われていたことを示す具体例として、三重県の斎宮跡で、ひらがなで「ぬるをわか」「つねなら」と墨書された土師器片(11世紀末〜12世紀前半頃)が見つかっています。
冤罪で消えた作者の怨念と遺書説

もし「咎なくて死す」というメッセージが意図的なものだとしたら、作者は一体誰なのでしょうか。
この暗号説では、いろは歌は単なる教材ではなく、冤罪で社会的に抹殺された人物が残した「遺書」であるという見方がなされます。
表向きは仏教の教えを説く美しい歌に見せかけながら、その裏に自らの無実と権力者への呪いを刻み込んだというストーリーは、非常にドラマチックであり、人々の想像力をかき立ててきました。
特に、47文字を重複させずに意味を通すという超人的な制約の中で、さらに暗号まで仕込むには並外れた知性が必要です。
そのため、歴史上でも特に優れた才能を持ちながら、悲劇的な最期を遂げた人物が作者の候補として挙げられることになります。
源高明や柿本人麻呂が候補とされる背景
作者候補としてよく名前が挙がる人物の一人が、平安時代の貴族、源高明(みなもと の たかあきら)です。
彼は醍醐天皇の皇子でありながら、969年の「安和の変」で謀反の疑いをかけられ、大宰府へ左遷されました。
当時の左遷は政治的な死を意味するため、「咎なくて死す」という状況に合致すると考えられています。
彼は『源氏物語』の光源氏のモデルの一人とも言われるほどの教養人であり、こうした高度な歌を作る能力があったと推測されています。
もう一人の有力な候補は、万葉集の歌人・柿本人麻呂です。
哲学者である梅原猛氏が著書で提唱した説によれば、人麻呂は高官であったものの政治闘争に敗れ、水死刑に処されたとされています(※この説は学術的には定説ではありません)。
梅原説では、いろは歌の中に「かきのもと」「ひとまろ」の名も隠されていると解読し、これが人麻呂の絶筆であると主張しました。
学術的な見解との違い
源高明や柿本人麻呂を作者とする説は、ミステリーとしては非常に興味深いですが、言語学や歴史学の観点からは否定的な意見が一般的です。あくまで「歴史ロマン」や「俗説」として楽しむのが良いでしょう。
江戸時代から囁かれた呪いの歴史
いろは歌を「不吉」とする感覚は、現代のネット社会で急に生まれたものではありません。
実は、江戸時代には既に似たような話が語られていました。
江戸中期の国学者、谷川士清(たにがわ ことすが)が著した辞書『倭訓栞(わくんのしおり)』には、いろは歌の7文字区切りの末尾を読むと「咎なくて死す」となることを指摘し、解釈とともに言及があります。
つまり、少なくとも江戸時代には、人々がこの歌に潜む「とがなくてしす」という並びを意識していたことになります。
日本人が長い歴史の中で、文字という文明的な道具の裏側に、非合理な「呪い」や「怨念」を見出してきたことがわかります。
いろは歌の意味は怖い都市伝説か真実か

前半では歴史的な暗号説について触れましたが、現代ではさらに進化した「新しい都市伝説」も生まれています。
キリスト教との関係や、メディア技術の発展に伴って生まれた逆再生の噂など、現代人が感じる「怖さ」の正体に迫ります。
隠されたキリスト教やイエスのメッセージ
近年、ネット上で特に話題になるのが、いろは歌とキリスト教の関係です。
この説では、いろは歌は弾圧された隠れキリスト教徒による信仰告白ではないかと推測されます。
よく語られる解読法の一つに、7文字×7行のグリッドの四隅(角)の文字をつなぐと「い・ゑ・す(イエス)」と読めるというものがあります。
また、各行の頭文字をつなげた「いちよらやあゑ」という音の並びを、古代ヘブライ語で「神ヤハウェの人」を意味する言葉の転訛だと解釈する説もあります。
さらに、いろは歌の作者を空海(弘法大師)とする古い俗説と結びつけ、「空海が中国で景教(ネストリウス派キリスト教)を学び、その教えをいろは歌に隠した」という壮大なストーリーが語られることもあります。
ただ、いろは歌の成立時期とされる平安期の日本で、キリスト教が社会的に存在していたことを示す一次史料は限られ、年代の整合性が課題になりやすい説です。
「文字配列から読める」ことと「当時の信仰告白である」ことは同一ではない、という切り分けが必要でしょう。
学術的な信憑性について
空海が作者であるという説は、使用されている仮名遣い(音韻)の年代が合わないため、現在の言語学では否定されています。キリスト教説もまた、言語学的な根拠は薄く、あくまで現代的な解釈の一つと捉えるのが賢明です。
わらべ歌にある「ヘブライ語説」と同じタイプの話も多いため、あわせて読んでおくと理解しやすくなります。
逆再生で聞こえる不可解な声の正体
デジタル技術が普及した現代ならではの怪談として、「いろは歌を逆再生すると呪いの言葉が聞こえる」という噂があります。
動画サイトなどで検証されることがありますが、具体的には「死ね」「苦しい」といった言葉に聞こえると言われることが多いようです。
しかし、これはパレイドリア効果(意味のない刺激の中に、意味のあるパターンを見いだしてしまう知覚の偏り)の一種である可能性が高いと言えます。
人間には、意味のないランダムな点や音の中に、知っているパターン(人の顔や言葉)を見つけ出そうとする習性があります。
かつてロック音楽のレコードを逆再生すると悪魔のメッセージが聞こえるという「バックマスキング」騒動がありましたが、それと同様に、不気味な雰囲気や予備知識を持って聞くことで、脳が勝手に意味のある言葉として補完してしまっていると考えられます。
歌ってはいけないタブーと処刑のイメージ
「いろは歌を最後まで歌ってはいけない」「歌うと不幸になる」といったタブーも、一部でまことしやかに囁かれています。
その根拠として、歌詞の内容を処刑の描写として読み替えるというグロテスクな解釈が広まっています。
例えば、「色は匂へど」を血の匂いや死臭と捉え、「散りぬるを」を首が落ちる様子、「有為の奥山」を死出の旅路や処刑場への道と解釈するものです。
これは「かごめかごめ」や「通りゃんせ」といったわらべ歌が、しばしば「口減らし」や「神隠し」の物語として語り直されるのと似た現象と言えます。
日常的に使う言葉の裏に、実は残酷な意味が隠されているのではないかと疑う心理が、こうした「やってはいけない」系の都市伝説を生み出しているのかもしれません。
本来は仏教の無常観を説く美しい歌

ここまで怖い話ばかりを紹介してきましたが、学術的・歴史的に認められている「正統な意味」についても触れておきましょう。
いろは歌の内容は、仏教経典『大般涅槃経(だいはつねはんぎょう)』に見られる四句の偈(「諸行無常、是生滅法、生滅滅已、寂滅為楽」)になぞらえたものと説明されることが一般的です。
SAT大蔵経テキストデータベース『大正新脩大藏經(SAT2018)』
雪山偈の「諸行無常(すべてのものは移ろいゆく)」という教えを、いろは歌では「色は匂へど 散りぬるを(美しい花もやがては散ってしまう)」と表現しています。
また、「是生滅法(これらは生じては滅するものである)」を「我が世誰ぞ 常ならむ(この世に永遠不変のものはいない)」と訳し、最終的には悟りの境地に至る決意を歌っています。
つまり、本来は死を恐れる歌ではなく、死や変化といった逃れられない運命(無常)を受け入れ、迷いを断ち切って安らかに生きようとする、非常に前向きで哲学的な歌なのです。
よくある質問:いろは歌の暗号・呪いは本当?
- Q「咎なくて死す」は、作者の遺書だと考えてよい?
- A
7字区切りで「とがなくてしす」と読めること自体は古くから知られていますが、作者が遺書として意図したと確定できる一次史料は見つかっていません。物語としての解釈が先行している面が大きいでしょう。
- Q「咎なくて死す」は「冤罪で処刑」の意味で確定?
- A
その解釈は有名ですが、辞書では「咎なく生を終える」といった説明も見られます。どちらが正しいと断定するより、「読みが分かれる」点が噂の温床になっています。
- Qいろは歌は歌ったら不幸になる?
- A
歌うこと自体を禁じる公的な根拠や確立した史料は一般に確認されていません。怖い解釈が「タブー物語」を生みやすい、という構図で捉えると整理しやすいです。
- Qキリスト教(ヘブライ語)説は信じてよい?
- A
文字配列から読めるという主張はありますが、成立時期や言語学的根拠の面で課題が指摘されやすい説です。結論を急がず、根拠の種類(史料・言語・年代)を分けて見るのが安全です。
結論:いろは歌の意味が怖いと感じる心理
いろは歌にまつわる「怖い」話の数々は、偶然の産物である可能性が高いと言えます。
「咎なくて死す」という並びも、確率的には奇跡的な偶然ですが、人間が後から意味を見出した結果であるという見方が専門家の間では主流です。
しかし、なぜ私たちはこれほどまでにいろは歌に恐怖を感じ、惹きつけられるのでしょうか。
それはおそらく、私たち日本人が「無常」という美意識の裏側に、常に「死」の気配を感じ取っているからではないでしょうか。
また、歴史上の敗者や冤罪で亡くなった人々に対し、「何か言い残したことがあるはずだ」と同情し、物語を補完しようとする「判官贔屓(ほうがんびいき)」の心理も働いていると考えられます。
いろは歌は、単なる文字の羅列を超えて、日本人の死生観や歴史への眼差しを映し出す鏡のような存在と言えるかもしれません。
記事の内容に関する注意
本記事で紹介した暗号説や都市伝説は、あくまで一つの解釈や俗説であり、歴史的事実として確定しているものではありません。エンターテインメントや文化的な考察としてお楽しみください。